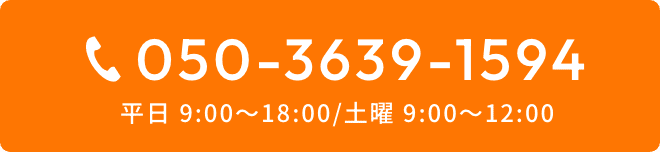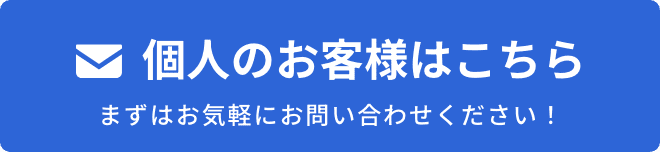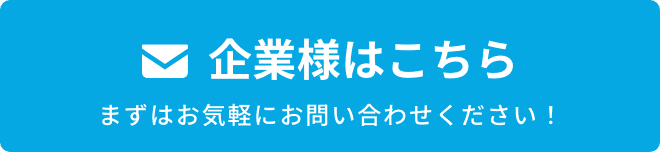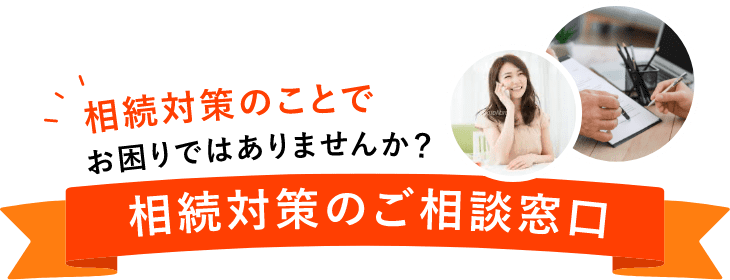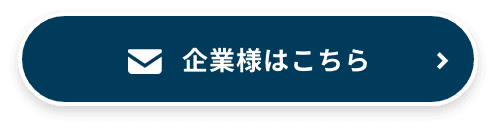ブログ
家族信託で兄弟トラブルを避けるための知識と対策|齋藤久誠公認会計士税理士事務所(東京都世田谷区)
家族信託は、相続や財産管理の新しい形として注目されている制度です。近年では高齢化が進み、認知症対策や事業承継などを目的として家族信託を導入する方が増えています。しかし、その一方で、家族間、特に兄弟間での意見の相違や誤解からトラブルに発展するケースも少なくありません。家族信託は「家族で信頼を形にする仕組み」であるからこそ、感情や関係性のもつれが問題を複雑にすることがあります。
東京都世田谷区にある齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、税務・法務・会計の観点から、生前の相続対策や家族信託の設計をサポートしています。本記事では、家族信託の基本から、兄弟間で起こりやすいトラブル、その防止策、そして成功事例までを詳しく解説します。

目次
家族信託で兄弟トラブルを避けるための基本知識
家族信託とは何か
家族信託とは、財産を信頼できる家族(受託者)に託し、委託者の意思に基づいて管理・運用し、その利益を受益者が受け取る仕組みです。生前の財産管理を家族内で完結できるため、遺言書や成年後見制度に代わる手段として注目されています。
たとえば、父親が自宅や預金を長男に信託し、父親の生活費や介護費として使うように契約しておけば、父親が認知症になっても、長男が適切に財産を管理し支出できるようになります。齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、こうした仕組みを法律・税務の両面からサポートし、家族間の信頼を基盤にした円滑な資産承継を実現しています。
家族信託の仕組みと流れ
家族信託の基本的な流れは、まず委託者(財産の持ち主)が受託者(信頼できる家族)と信託契約を結びます。次に、信託財産として指定した不動産や預貯金の名義を受託者名義に変更し、受託者が管理・運用を行います。信託契約で定めた目的に従い、最終的に受益者へ財産が帰属するというのが全体の流れです。
この際に重要なのは、契約内容を明確にし、税務上の影響を十分に把握することです。東京都世田谷区の齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、契約前の設計段階から税負担を最小化できるようにサポートを行っています。
家族信託のメリットとデメリット
家族信託の大きなメリットは、委託者が判断能力を失っても、受託者が代わりに財産を管理できる点です。成年後見制度と比べて柔軟性が高く、家族間で意思決定がしやすいのも特徴です。さらに、遺言書に比べて自由度が高く、将来の財産分配や資産運用を細かく設定できます。
一方で、制度を十分に理解せずに契約すると、思わぬ税務リスクや家族間の不信感を招く可能性があります。特に兄弟間で「公平性」が問題となりやすく、事前に全員が納得できる説明が不可欠です。齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、こうしたリスクを防ぐため、契約時の面談に家族全員が同席し、合意形成を図ることを推奨しています。

兄弟間で起こりやすい家族信託トラブル
受託者選びを巡る対立
兄弟の中から受託者を選ぶ際、「誰が最も信頼できるか」という点で意見が分かれることがあります。たとえば、長男が受託者に選ばれた場合、次男が「財産を独占されるのでは」と疑念を抱くことがあります。こうした感情のずれが、後のトラブルの火種となるのです。
齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、兄弟間での公平性を保つため、共同受託者制度を提案することがあります。複数人で財産を管理すれば、チェック機能が働き、相互の信頼関係を維持しやすくなります。
財産分配に関する不満
信託財産の運用益や最終的な帰属先を決める際、兄弟の間で不公平感が生じることがあります。特に、介護を担当した兄弟とそうでない兄弟との間で、「負担と利益が釣り合わない」と感じる場合が多いです。
こうした事態を避けるためには、家族信託を設計する段階で「誰がどのように貢献してきたか」を明確にし、それを契約書や家族会議の議事録に残すことが大切です。齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、実際の生活実態に合わせた分配ルールを提案しています。
情報共有の不足による誤解
家族信託の運用が始まった後、受託者から他の兄弟への情報共有が十分でないと、「何をどう管理しているのか分からない」と不信感が生まれます。この状態が続くと、わずかな誤解でもトラブルに発展します。
そのため、定期的な家族会議や報告書の提出を行い、透明性を確保することが重要です。東京都世田谷区の齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、信託報告書の作成や収支確認を第三者として支援し、信頼関係を維持できるようサポートしています。

トラブルを防ぐための家族信託の設計方法
受託者の選定と役割の明確化
受託者を選ぶ際は、単に「信頼できる人物」だけでなく、「責任感」「経理能力」「コミュニケーション能力」などを考慮する必要があります。さらに、契約書の中で受託者の職務範囲や権限を具体的に明記することが不可欠です。曖昧な記載があると、兄弟間の解釈の違いから衝突を招くことになります。
齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、各家庭の人間関係を丁寧にヒアリングし、最適な受託者構成を提案しています。
信託契約書の重要性
信託契約書は、家族信託の根幹をなす文書です。契約書の文言一つで、税務処理や登記の可否が変わることもあります。市販のテンプレートを利用するのではなく、個別事情に合わせた契約書を専門家が作成することが大切です。
東京都世田谷区の齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、税理士・弁護士・司法書士が連携し、法律的にも税務的にも有効な契約書を作成しています。
定期的な家族会議の実施
信託を円滑に運用するには、契約後も定期的に家族会議を開き、財産状況を共有することが重要です。たとえば、年に一度の報告会を設けることで、受託者の業務を可視化し、兄弟全員の安心感を保つことができます。齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、信託契約後のアフターフォローとして家族報告会の開催を推奨しています。

トラブルを避けるための具体的な対策
信託監督人や受益者代理人の活用
第三者である信託監督人や受益者代理人を設けることで、公平性と透明性を高めることができます。家族間での直接的な意見の衝突を防ぎ、専門家の中立的な判断を取り入れることで、長期的な信頼関係を保てます。
透明性のある財産管理
信託口座の開設や定期的な会計報告書の提出など、財産の流れを誰もが確認できる体制を整えることが重要です。東京都世田谷区の齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、信託専用会計の仕組みを導入し、受託者が安心して業務を遂行できるよう支援しています。
専門家のサポートを受ける
家族信託は法律・税務・登記が複雑に絡み合う制度です。独自判断で進めると、後で修正できない問題に発展する恐れがあります。齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、家族信託に精通した専門チームが、設計から税務申告、アフターフォローまで一貫してサポートしています。

ケーススタディ:成功例と失敗例から学ぶ
成功した家族信託の事例
世田谷区内にお住まいのご家庭では、父親の認知症対策として家族信託を導入しました。信託契約を結ぶ前に全員で家族会議を重ね、受託者・受益者の役割を明確にしたことで、相続発生後も兄弟間でトラブルは一切ありませんでした。
齋藤久誠公認会計士税理士事務所が税務・法務の両側面からサポートし、透明性ある財産管理を実現できたことが成功の要因でした。
失敗した家族信託の事例
一方で、インターネットの情報だけを頼りに自己流で契約書を作成したケースでは、契約内容が税法上の要件を満たしておらず、結果的に贈与税の課税対象となってしまいました。さらに、受託者が兄弟の一人に偏っていたため、他の兄弟から不満が噴出。
専門家の確認を怠ったことで、修正にも時間と費用がかかりました。このようなトラブルは、初期段階で専門家に相談することで防ぐことができます。

Q&A
家族信託はいつ始めるのが良いですか?
家族信託は、委託者の意思能力が十分にある段階で着手するのが最適です。判断能力が低下してからでは契約が無効となるおそれがあり、成年後見など別制度の検討が必要になります。早期に設計を進めれば、認知症対策や資産の用途指定、将来の受益者変更などの条項を柔軟に織り込めます。東京都世田谷区の齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、初回面談で家族関係や資産構成、希望するライフプランを丁寧に整理し、無理のないスケジュールで家族信託の骨子案を提示します。準備期間中は必要資料の洗い出しや各金融機関の運用ルール確認、司法書士・弁護士との分担設計まで併走し、契約後の運用報告や税務面の点検まで一体的に支援します。
税金はかかりますか?
家族信託は設計次第で課税関係が変わります。委託者課税型の基本設計であれば、受益者を委託者本人とし、受託者は管理に徹するため、契約時に贈与税は通常発生しません。一方、受益者を子に設定するなど経済的利益の移転が生じる設計では贈与税や相続税評価の論点が生じ、信託不動産の譲渡・交換を伴えば譲渡所得税や登録免許税・不動産取得税の検討も必要です。齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、家族信託の目的を損なわずに税負担を最小化する条項設計と、年度ごとの所得区分の判定、信託計算書の整備、受益者別の確定申告サポートまで一貫対応します。東京都世田谷区を中心に、地元の金融機関・不動産業者とも連携し、実務運用で齟齬が出ないよう事前調整を行います。
兄弟のうち一人が反対している場合はどうすれば良いですか?
家族信託は契約行為であり、委託者の自由意思で締結できますが、長期の運用を見据えると兄弟全員の理解と参加が望ましいです。反対の背景には情報不足や公平性への不安があることが多いため、資産の現状、信託の目的、受託者の権限と義務、報告の頻度、終了時の帰属先を明確に言語化し、定期報告や閲覧方法を合意してから署名に進むと不信の芽を摘めます。齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、第三者的立場で家族会議をファシリテーションし、必要に応じて信託監督人や受益者代理人を設置して透明性を担保する設計を提案します。東京都世田谷区内での対面相談に加え、遠方の兄弟にはオンラインで同内容の説明を行い、情報非対称を解消します。
不動産を信託に含めることはできますか?
不動産は家族信託の中心的な対象です。委託者から受託者へと名義変更を行い、信託目録に物件情報と管理・処分権限を明記します。賃貸中であれば賃料の受領・修繕・更新の権限、売却を予定するなら売却条件や収益の帰属先、代替不動産の取得可否などを具体的に規定します。登記は信託登記が必要で、信託の旨が公示されることで第三者対抗力を備えます。齋藤久誠公認会計士税理士事務所は司法書士と連携し、東京都世田谷区の物件はもちろん他都県の登記にも対応し、固定資産税や都市計画税の納付、減価償却や修繕費の取扱いなど信託会計まで含めて実務運用を支援します。管理負担の大きい空き家対策や売却代金の生活費充当といった目的設計も得意分野です。
東京都世田谷区以外でも相談できますか?
地元密着での対面支援を重視しつつ、東京都世田谷区外の相談にもオンラインで広く対応しています。初回面談はビデオ会議で実施し、身分確認や資産資料の授受はセキュアな共有環境を用いるため遠方でも支障はありません。必要に応じて現地の司法書士・不動産事業者・金融機関と連携し、家族信託の登記・口座開設・家屋調査など地域固有の実務も円滑に進めます。齋藤久誠公認会計士税理士事務所は、多拠点の家族や複数県に跨る不動産ポートフォリオを想定した条項設計を標準化しており、移転後の住所変更や受託者交代にも耐える運用フローを用意しています。面談後は議事要旨と次回までのタスクを文書化し、家族全員が同じ前提で判断できる体制を整えます。
家族信託と遺言・成年後見の違いは何ですか?
遺言は死亡時の財産承継を指定する最終意思であり、生前の管理・運用を直接規律する力は弱い制度です。成年後見は判断能力が低下した後に家庭裁判所の監督下で財産保護を図る枠組みで、柔軟な資産運用や贈与・組み替えは制約が大きい傾向にあります。家族信託は生前から死後までの管理・承継を連続的にデザインでき、受託者の権限設計によって機動的に意思を実現できます。もっとも、家族信託だけでは遺留分や相続人調整を全て解決できないこともあるため、遺言や任意後見、死後事務委任と併用して全体最適を図るのが実務的です。齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、家族信託を中核に、付随する公正証書遺言や任意後見契約の要否を見極め、東京都世田谷区の公証役場手続きまで一括で段取りします。
費用感と期間はどのくらいですか?
費用は資産の種類や条項の複雑度、関与士業の範囲で変動します。一般的には、設計・契約書作成・登記・税務アドバイス・運用初期サポートを含めたパッケージで見積り、信託監督人設置や複数不動産の編入、持分調整などがある場合は個別に加算します。期間はヒアリングから草案作成、家族会議を重ねて確定、登記・口座開設・初期仕訳の整備までを含めて、シンプルな案件でおおむね一〜二か月、論点が多い場合は三か月程度を目安に想定します。齋藤久誠公認会計士税理士事務所では、初回相談で全体スケジュールを可視化し、必要資料の一覧、関与士業の役割分担、家族信託の運用規程サンプルまで提示し、途中で迷いが生じないよう伴走します。

まとめ
家族信託は、家族の意思を途切れさせずに生活と資産を守る実務的な器であり、相続や認知症対策、事業承継、空き家対策など多様な課題を一つのフレームに収められる点に真価があります。制度そのものは柔軟ですが、条項の一文や手続きの一段取りが数年後の税務・法務に波及するため、目先だけでなく長期の見取り図を描く設計力が求められます。東京都世田谷区の齋藤久誠公認会計士税理士事務所は、家族構成や資産の形、兄弟間の関係性を丁寧に汲み取り、必要十分な透明性と手離れの良さを両立させた家族信託を提案します。家族会議の進め方、信託口座の運用、会計報告のフォーマット、税務申告の段取り、信託終了時の出口戦略まで一連のプロセスを標準化し、家族が安心して日常に専念できるよう下支えします。
家族信託の検討を始める最良の時期は、家族が元気で会話ができる今です。資産をどう使い、誰の暮らしをどう支え、どのように次世代へ渡すのかという具体の言葉が、信託契約という形になったとき、家族は迷いから解放されます。齋藤久誠公認会計士税理士事務所は、東京都世田谷区で培った地域連携と専門実務で、初回相談から設計・登記・会計・税務・運用フォローまでを一気通貫で支援し、家族の想いを現実に変えます。兄弟が安心して未来を語れる環境づくりの第一歩として、家族信託の個別相談にお越しください。

(東京税理士会玉川支部所属(登録番号:139151号)
FAQ
よくあるご質問
- 電話・メールでの税務相談は可能ですか?
- 当事務所の方針としまして、ご相談の際には、直接お会いしてお話させていただいております。ただし、場合によっては、お電話にて相談を承る場合もあります。詳しくは、一度お電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 相談に行く際、事前に準備しておくべきことはありますか
- 初回面談はお客様のご相談事項をお伺いすることが中心です。ご相談事項に関連する資料をご準備ください。
- 費用はいくらかかりますか?
- お支払いいただく費用はご依頼事項により異なります。ご依頼いただく前にお見積書を作成させていただきますのでご依頼ください。
- 駐車場はありますか?
- 当事務所は専用駐車場を用意しておりません。近隣の駐車場をご利用いただくか公共交通機関でのご来訪をお願いいたします。
- 予約なしで相談できますか?
- 当事務所は完全予約制とさせていただいております。ご相談をご希望の際は、事前に電話またはメールでのお問合せをお願い致します。
information
事務所情報

- 住所
-
〒158-0094
東京都世田谷区玉川3-11-1柳小路東角3階310
- tel
- 050-3639-1594
- 営業時間
-
平日 9:00〜18:00 / 土曜 9:00〜12:00
当社は完全予約制となっております。
- メールアドレス
- saito@cpatax-office.com
- 定休日
- 日、 祝日
- 最寄り駅
- 東急田園都市線・大井町線『二子玉川』駅 徒歩3分