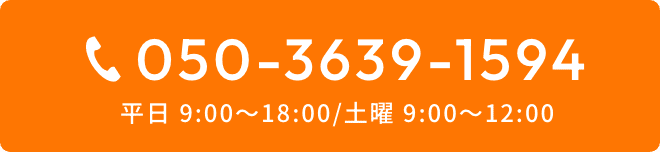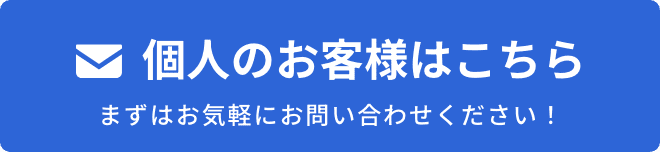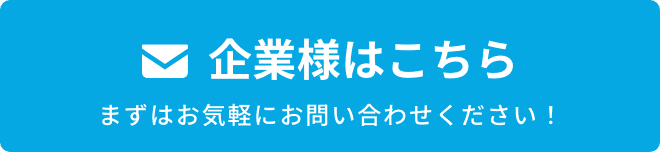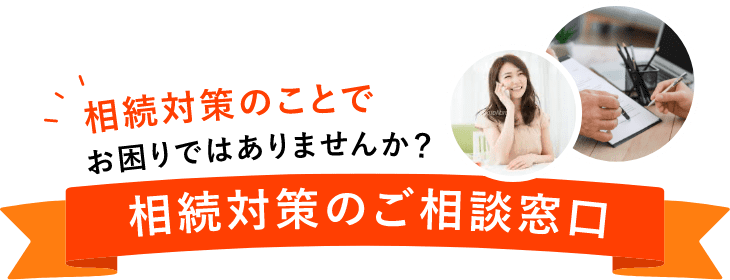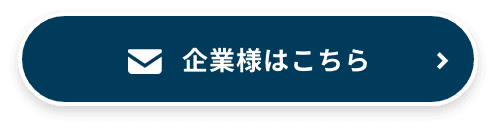ブログ
相続 名義変更 いつまでにすべき?期限と手続きの詳細解説|齋藤久誠公認会計士・税理士事務所
相続の名義変更はいつまでに行うべきか?法的期限や税務リスク、手続きを詳細に解説。遅れると発生するデメリットも紹介。
目次
1. 相続の名義変更とは?
相続の名義変更とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産の名義を相続人に変更する手続きのことです。不動産・預貯金・自動車・証券などの財産が該当します。相続が発生すると、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決定する必要があります。その後、各財産の名義を正式に相続人のものへ変更することで、売却や活用が可能となります。
名義変更を行うことで、相続財産の適正な管理が可能となり、第三者とのトラブルを防ぐことができます。例えば、不動産の登記変更を怠ると、将来的に権利関係が複雑になり、相続人間での争いが発生する可能性があります。また、銀行口座の名義変更を行わないと、預金の引き出しができなくなり、生活資金や事業運営に支障をきたす恐れもあります。
名義変更には、それぞれの財産に応じた手続きが必要です。例えば、不動産の名義変更は法務局で登記申請を行い、銀行口座は金融機関の指定する手続きを経る必要があります。証券や自動車の名義変更も、各機関で定められた手続きを踏まなければなりません。

なぜ名義変更が必要なのか?
名義変更を行わないと、相続財産を自由に使うことができず、売却や処分ができないためです。また、相続税の申告などにも影響を与えることがあります。相続財産の所有者が正式に変更されないと、法律上の権利が曖昧なままとなり、金融機関や不動産取引の際に問題が発生することがあります。
さらに、相続財産の名義変更を放置すると、将来的な相続人の増加により手続きがより複雑になる可能性があります。特に、不動産の名義変更を行わないまま何世代も経過すると、相続人の数が増え、遺産分割協議が困難になるケースもあります。そのため、相続が発生した際には、できるだけ早く名義変更の手続きを行うことが望ましいです。
相続税の申告にも影響を与えるため、期限内に手続きを進めることが重要です。相続税の申告期限は被相続人の死亡から10か月以内であり、それまでに遺産分割が完了していないと、相続税の負担が増える可能性があります。例えば、未分割の状態では税制上の優遇措置が適用されないことがあり、税負担が大きくなる場合があります。
このように、相続の名義変更は単なる形式的な手続きではなく、法律的・税務的に重要な意味を持ちます。スムーズに相続財産を引き継ぎ、トラブルを防ぐためにも、早めに手続きを進めることが大切です。
2. 名義変更の必要なケース
名義変更が必要になる代表的なケースを見てみましょう。

不動産の名義変更
土地や建物の名義変更は、登記手続きを通じて行います。登記を行わないと、第三者に対して所有権を主張できません。また、登記をしないまま長期間放置すると、権利関係が複雑になり、相続人間でトラブルが発生する原因となることもあります。
不動産の名義変更には、遺産分割協議書や被相続人の戸籍謄本、固定資産評価証明書などの書類が必要になります。相続登記の手続きを行う際は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
預貯金の名義変更
銀行口座の名義を変更しないと、預金を引き出すことができず、生活に支障をきたす可能性があります。特に、故人の口座に光熱費や税金の引き落とし設定がされていた場合、滞納によるトラブルが発生する可能性があるため、早めの対応が必要です。
預貯金の名義変更手続きには、銀行ごとに異なる書類が求められることが多いですが、一般的には、被相続人の戸籍謄本、相続人の本人確認書類、遺産分割協議書、銀行指定の申請書が必要となります。各金融機関のルールを確認し、必要書類を揃えた上で手続きを進めましょう。
自動車・証券の名義変更
自動車の名義変更を行わないと、運輸局での手続きが完了せず、売却や譲渡ができなくなります。また、自動車税の納付義務も変更されないため、トラブルの原因になることがあります。
証券(株式など)の名義変更も重要です。被相続人が株式を所有していた場合、証券会社に申請を行わない限り、株の売却や配当の受け取りができなくなります。証券会社の指定する手続きを確認し、必要な書類を準備することが大切です。
名義変更を怠ると、後々の手続きが煩雑になるため、相続が発生したらできるだけ早めに対応することをおすすめします。
3. 相続 名義変更の期限と法律上の規定
相続の名義変更には、法律で定められた明確な期限はありませんが、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

相続税の申告期限(10か月)
相続税の申告期限は「被相続人の死亡から10か月以内」とされています。この期間を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があります。相続税の申告は、名義変更の前後に関わらず必要になるため、早めに準備を進めることが重要です。
相続税を適正に申告するためには、相続財産の評価を行い、適用できる控除や特例を確認する必要があります。財産の種類によって評価方法が異なるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
登記義務の改正(2024年4月以降)
2024年4月1日以降、相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この改正により、不動産の相続登記を放置することのリスクが大きくなりました。従来は任意だった登記が義務化されたことで、手続きを怠ると罰則を受ける可能性があるため、早めに手続きを進めることが求められます。
不動産の相続登記には、必要書類の準備や登記申請手続きが含まれます。法務局への提出が必要となるため、手続きをスムーズに進めるためにも、司法書士などの専門家に相談することが望ましいです。
このように、相続の名義変更には期限や法的な義務が関わるため、速やかに対応することが重要です。
4. 名義変更の具体的な手続き
名義変更の流れを解説します。
不動産の名義変更手続き
不動産の名義変更には、いくつかのステップが必要です。
- 遺産分割協議の完了
まず、相続人間で不動産の分配について合意し、遺産分割協議書を作成します。この協議書には、全相続人の署名と実印が必要です。 - 必要書類の準備
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
これらの書類を揃えることで、法務局での手続きがスムーズに進みます。
- 法務局での登記申請
書類を揃えたら、管轄の法務局に登記申請を行います。手続きが完了すると、正式に名義が変更されます。
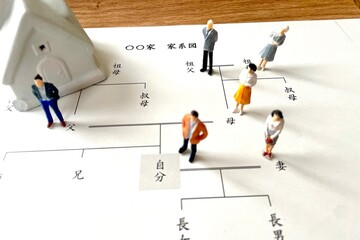
預貯金の名義変更手続き
銀行口座の名義変更を行う際は、以下の手続きを踏みます。
- 銀行に申請
被相続人が利用していた金融機関に連絡し、相続手続きの申請を行います。各銀行ごとに必要な書類や手続きの流れが異なるため、事前に確認しておくことが重要です。 - 必要書類の提出
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の本人確認書類
- 遺産分割協議書
- 銀行の相続手続き申請書
これらの書類を金融機関に提出し、審査を受けます。
- 口座の相続手続きの完了
審査が完了すると、相続人の口座へ相続された預貯金が振り込まれ、名義変更が完了します。
注意点:
- 金融機関によっては、名義変更に数週間かかる場合があります。
- すべての相続人が協力しないと、手続きが進まないケースもあります。
このように、財産の種類ごとに異なる名義変更手続きがありますので、早めに対応することが重要です。
5. 相続税と名義変更の関係
相続税と名義変更は密接な関係があります。相続税の申告が必要な場合、適切な期限内に手続きを行わないと、税務上のペナルティが発生する可能性があります。
相続税申告が必要なケース
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要になります。この基礎控除額を超えると、相続税を計算し、納付義務が発生します。
また、相続税の申告が必要な場合、遺産分割協議を速やかに行い、財産の名義変更を進めることが重要です。
特に不動産の場合、評価方法が異なり、固定資産税評価額や路線価方式などを基に算定されます。

相続税の納税期限
相続税の納税期限は被相続人の死亡から10か月以内です。この期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生するため、注意が必要です。
相続税の納税方法には、現金一括納付と分割納付(延納)があり、場合によっては物納も認められることがあります。納税資金を確保するためにも、預貯金や不動産の名義変更を早めに進めることが重要です。
さらに、相続税の申告期限内に遺産分割が完了していない場合、小規模宅地の特例などの税制優遇措置が適用できない可能性があります。そのため、速やかに名義変更を行い、税務申告を完了させることが望ましいです。
このように、相続税の申告と名義変更には密接な関係があるため、計画的に手続きを進めることが重要です。
6. 名義変更の期限を過ぎた場合のリスク
相続の名義変更には明確な期限がない場合もありますが、遅れることで発生するリスクが多くあります。特に、不動産や預貯金の名義変更を怠ると、後々の手続きがより複雑になり、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
不動産登記を怠った場合
2024年4月以降、不動産の相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、登記を怠った場合、不動産の売却や担保設定ができなくなるだけでなく、次の相続時に権利関係がさらに複雑になり、名義変更の手続きがより困難になります。特に、相続人が増えると遺産分割協議が難航し、争族(相続争い)につながるリスクが高まります。
不動産の名義変更をスムーズに進めるためには、司法書士に相談し、早めに手続きを開始することが重要です。遺産分割協議が完了したら、できるだけ早く法務局で登記申請を行うようにしましょう。

預貯金の引き出しができなくなる
金融機関によっては、手続きの遅延により口座凍結のリスクがあります。被相続人の死亡が確認されると、多くの銀行ではその口座を凍結し、遺族が自由に引き出すことができなくなります。
特に、生活費や事業資金として預金を使用していた場合、口座が凍結されることで日常生活や業務運営に大きな支障をきたす可能性があります。そのため、相続が発生したら速やかに銀行に連絡し、名義変更の手続きを進めることが重要です。
預貯金の名義変更には、以下の書類が必要となります。
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人の本人確認書類
- 銀行所定の相続手続き書類
これらを揃えた上で、各金融機関の指示に従って手続きを進めることで、速やかに預貯金の名義変更を完了させることができます。
早めの手続きを行うことで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな財産管理が可能になります。
7. 名義変更に必要な書類一覧
相続の名義変更には、財産の種類ごとに異なる書類が必要です。事前に必要書類を揃えておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
不動産登記の必要書類
不動産の名義変更(相続登記)には、以下の書類が必要となります。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの記録が含まれるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(相続人が明確になるよう全員分を取得)
- 遺産分割協議書(必要な場合、相続人全員の合意がある場合)
- 固定資産評価証明書(市区町村役場で取得可能、登記に必要な評価額の証明)
- 相続関係説明図(法務局の登記官が関係を確認しやすくするための書類)
- 登記申請書(法務局に提出する正式な申請書類)
- 印鑑証明書(遺産分割協議書に署名・押印した相続人のもの)
登記手続きには専門的な知識が求められるため、司法書士に依頼することも検討するとよいでしょう。

預貯金の名義変更の必要書類
銀行口座の名義変更を行うためには、以下の書類が必要です。
- 被相続人の死亡届出受理証明書(または死亡診断書のコピー)
- 相続人の戸籍謄本(相続人であることを証明)
- 相続人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
- 金融機関指定の相続手続き申請書(各銀行のフォーマットに準ずる)
- 遺産分割協議書(相続人全員の合意が必要な場合)
- 印鑑証明書(相続手続きに必要な場合)
- 口座解約届(金融機関によって求められることがある)
金融機関ごとに必要書類が異なるため、事前に各銀行の公式サイトや窓口で確認しておくとスムーズに進められます。
ポイント:
- 口座の凍結を避けるために、早めに手続きを進める。
- 相続人全員の同意が必要な場合が多いため、手続き前に話し合いを済ませておく。
このように、不動産や預貯金などの財産の種類に応じた書類を適切に用意することが、スムーズな名義変更につながります。
8. スムーズな名義変更のためのポイント
相続手続きを円滑に進めるためには、事前の準備が非常に重要です。遅延やトラブルを避けるために、以下の点を意識しましょう。
遺産分割協議を早めに進める
名義変更をスムーズに行うためには、まず遺産分割協議を早めに進めることが不可欠です。相続人間での意見がまとまらないと、名義変更手続きを進めることができず、遅延が発生する原因となります。
遺産分割協議では、以下の点を話し合うことが重要です。
- 相続財産の分配方法
- 各相続人の同意を得るための調整
- 遺産分割協議書の作成
特に、不動産や預貯金の相続については、相続人全員の合意が必要な場合が多く、早めに協議を開始することでスムーズな名義変更につながります。協議がまとまらない場合は、専門家に相談し、円満な解決を図ることをおすすめします。

司法書士・税理士に相談する
相続の名義変更手続きは、法律や税務に関わるため、専門家のアドバイスを受けることで手続きをスムーズに進めることができます。特に、以下のようなケースでは専門家のサポートが有益です。
- 不動産の名義変更: 司法書士に依頼することで、法務局での登記手続きがスムーズに進みます。
- 相続税申告: 税理士に相談することで、適切な申告手続きを行い、節税対策も可能になります。
- 遺産分割の調整: 遺言書がない場合や、相続人間で意見が異なる場合、弁護士や行政書士に依頼することで、トラブルを避けることができます。
専門家に依頼することで、書類の不備や手続きの遅れを防ぎ、安心して名義変更を完了させることができます。
必要書類を事前に揃えておく
名義変更手続きを迅速に進めるためには、必要な書類を事前に準備することが大切です。不動産登記や預貯金の名義変更には、多くの書類が必要となるため、相続発生後すぐに収集を始めるとよいでしょう。
代表的な必要書類には以下のものがあります。
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書(必要な場合)
- 印鑑証明書
- 金融機関の指定書類
これらの書類を揃えることで、スムーズに手続きを進めることが可能になります。
手続きのスケジュールを立てる
相続の名義変更には、相続税の申告期限(10か月以内)や、不動産登記の義務化(3年以内)などの期限が設定されています。スケジュールを立てて、計画的に手続きを進めることが重要です。
特に、不動産の相続登記は2024年4月から義務化され、3年以内に手続きを完了しないと過料が科される可能性があります。相続税の申告期限も考慮しながら、早めに対応することが求められます。
9. よくある質問(FAQ)
相続の名義変更に関して、よくある質問をまとめました。
名義変更をしないとどうなる?
不動産の場合、名義変更をしないと以下のような問題が発生する可能性があります。
- 売却ができない:名義が被相続人のままだと、不動産を売却することができません。
- 担保設定ができない:融資を受ける際に不動産を担保として使えません。
- 相続人間のトラブルの原因になる:将来的に相続人が増えたり、権利関係が複雑になったりすることで、遺産分割の協議が難航する可能性があります。
- 登記義務違反になる:2024年4月以降、相続登記が義務化されており、3年以内に登記を行わないと過料が科される可能性があります。
預貯金の場合、金融機関によっては口座が凍結され、相続手続きが完了するまで引き出しができなくなるため、生活資金や事業資金に支障が出る可能性があります。

期限を過ぎても手続きできる?
名義変更の手続きは期限を過ぎても可能ですが、以下のようなリスクが発生するため、できるだけ早めに対応することが推奨されます。
- 税務上のペナルティ:相続税の申告期限(10か月)を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があります。
- 登記の義務化による罰則:不動産の場合、3年以内に登記を行わないと、最大で10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 相続人が増える可能性:時間が経つと、相続人が亡くなったり、次の世代に権利が引き継がれることで、相続人の数が増え、手続きがより複雑になります。
- 必要書類の取得が困難になる:戸籍謄本や相続関係を証明する書類は時間が経つと取得しにくくなり、手続きがさらに遅れる原因となります。
名義変更の手続きをスムーズに行う方法は?
名義変更をスムーズに行うために、以下の点を意識しましょう。
期限を意識して計画的に進める:相続税の申告期限や登記の義務化など、期限を考慮したスケジュールを立てて手続きを行いましょう。
遺産分割協議を早めに進める:相続人間での合意形成を早期に行うことで、名義変更手続きを迅速に進めることができます。
専門家に相談する:司法書士や税理士などの専門家に依頼することで、手続きの遅れを防ぐことができます。
必要書類を事前に揃える:登記申請や金融機関での手続きをスムーズにするために、必要書類を事前に準備しておくことが重要です。
まとめ
相続の名義変更は、不動産や預貯金などの財産をスムーズに引き継ぐために不可欠な手続きです。特に、2024年4月以降の不動産登記義務化により、3年以内の手続きが求められるため、早めの対応が重要です。
名義変更の遅れは、売却や担保設定の制約、相続人間のトラブル、税務上のペナルティなど、さまざまなリスクを伴います。遺産分割協議を早めに進め、必要書類を事前に揃えることがスムーズな名義変更につながります。
名義変更の手続きに関して不安や疑問がある場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
相続手続きに関するご相談は、ぜひ齋藤久誠公認会計士・税理士事務所へお任せください。豊富な経験を活かし、円滑な手続きをサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

(東京税理士会玉川支部所属(登録番号:139151号)
FAQ
よくあるご質問
- 電話・メールでの税務相談は可能ですか?
- 当事務所の方針としまして、ご相談の際には、直接お会いしてお話させていただいております。ただし、場合によっては、お電話にて相談を承る場合もあります。詳しくは、一度お電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 相談に行く際、事前に準備しておくべきことはありますか
- 初回面談はお客様のご相談事項をお伺いすることが中心です。ご相談事項に関連する資料をご準備ください。
- 費用はいくらかかりますか?
- お支払いいただく費用はご依頼事項により異なります。ご依頼いただく前にお見積書を作成させていただきますのでご依頼ください。
- 駐車場はありますか?
- 当事務所は専用駐車場を用意しておりません。近隣の駐車場をご利用いただくか公共交通機関でのご来訪をお願いいたします。
- 予約なしで相談できますか?
- 当事務所は完全予約制とさせていただいております。ご相談をご希望の際は、事前に電話またはメールでのお問合せをお願い致します。
information
事務所情報

- 住所
-
〒158-0094
東京都世田谷区玉川3-11-1柳小路東角3階310
- tel
- 050-3639-1594
- 営業時間
-
平日 9:00〜18:00 / 土曜 9:00〜12:00
当社は完全予約制となっております。
- メールアドレス
- saito@cpatax-office.com
- 定休日
- 日、 祝日
- 最寄り駅
- 東急田園都市線・大井町線『二子玉川』駅 徒歩3分