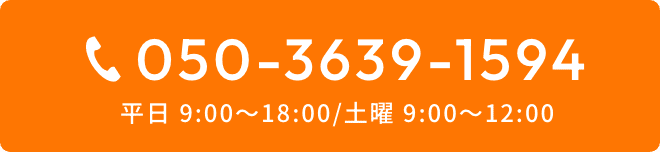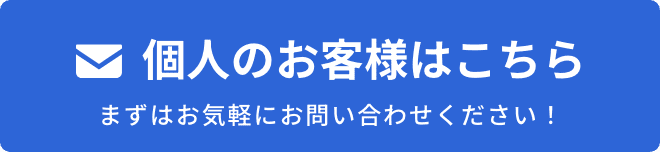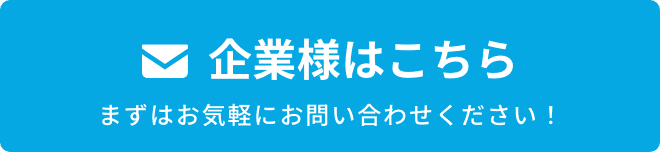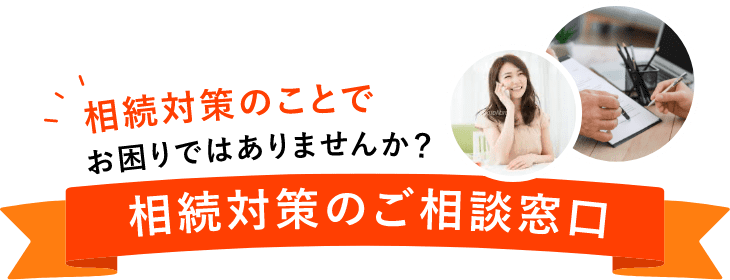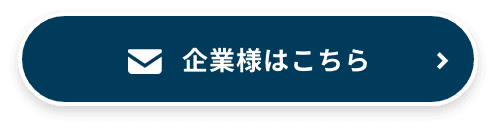ブログ
相続した家を売却する際の税金とは?東京都世田谷区「齋藤久誠公認会計士・税理士事務所」が詳しく解説

相続によって家を取得したあと、売却を検討する方が増えています。特に東京都世田谷区のように地価が高いエリアでは、不動産の売却によって多額の資金が動くことも少なくありません。しかし、その際に問題となるのが相続した家を売却する際の税金の負担です。
売却により得た利益には所得税や住民税が課税されるケースがあり、また相続税をすでに支払っている場合には特例の適用が受けられる可能性もあります。この記事では、齋藤久誠公認会計士・税理士事務所が、相続した家を売却する際に必要となる税金の仕組みや節税方法について、専門的にかつわかりやすく解説いたします。
目次
相続した家を売ると税金がかかるのか?

相続と譲渡所得の基本関係
相続によって取得した家を売却した場合、その売却益に対して課税されるのは譲渡所得税です。譲渡所得とは、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益のことで、取得した家にどれだけの価値があり、それをいくらで売ったのかが課税の判断基準になります。
譲渡所得税は「所得税」と「住民税」に分かれて課税され、税率は保有期間によって短期(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下)と長期(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超)で異なる点も重要です。ただし、相続で取得した不動産の場合、被相続人の所有期間を引き継ぐことが認められています。そのため、被相続人が長年住んでいた家を相続した場合、多くは「長期譲渡所得」として扱われ、税率も比較的軽減されます。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、次の式で計算されます。
譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)
このとき、「取得費」は被相続人が家を購入した当時の価格ですが、古い不動産で取得費が不明な場合には、概算取得費(譲渡価格の5%)を用いることも可能です。また、仲介手数料や登記費用、測量費などは「譲渡費用」として計上できます。
相続税の取得費加算の特例
相続時に相続税を支払っていた場合、その一部を「取得費」に加算できる制度があり、これを取得費加算の特例といいます。この制度を活用すると、譲渡所得を減らし、結果として課税額も軽減できます。
ただし、相続開始から3年10ヶ月以内に売却しないとこの特例は使えないため、売却時期の判断も重要になります。
譲渡所得の特別控除
居住用財産であれば、「3,000万円の特別控除」が受けられるケースもあります。被相続人が住んでいた家を売却する際に適用できる可能性があり、この特例を利用すれば、譲渡所得から3,000万円を差し引いて課税額を抑えることが可能です。
ただし、適用には一定の条件があり、条件を満たさない場合には対象外になる可能性もあります。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所による実践サポート
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、相続した家の売却に伴う税金について、計算・申告・節税対策まで一括サポートしています。お客様の状況に応じて、
・取得費加算の特例の適用可否の判断 ・3,000万円控除の条件の確認と書類準備 ・売却時期の最適化による節税効果の最大化 ・譲渡所得税の申告書作成
などを実施し、不動産会社では得られない税務視点からのアドバイスを提供しています。特に東京都世田谷区のような評価の高い不動産が多い地域では、売却益も大きくなりやすく、税金対策の重要性も高まります。
さらに当事務所では、税理士に加え、司法書士・不動産会社・弁護士とのネットワークを活かし、遺産分割や登記、売却契約に至るまで総合的な支援体制を整えています。税務申告だけでなく、家族間の調整や資産活用も含め、お客様の想いを実現する伴走型の相続支援を行っております。
相続した家を売却する際の注意点

相続登記を済ませていないと売却できない
相続した家を売却するには、まず所有者名義を自分に変更する「相続登記」が必要です。これは、被相続人(亡くなった方)の名義のままでは売却契約を締結できないからです。相続登記を行わなければ、買主側の金融機関の融資も下りず、売却自体が成立しません。
また、2024年4月からは相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記を行わなければ10万円以下の過料が科される可能性もあります。売却を急ぐ場合でも、この手続きを後回しにすることはできません。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、司法書士と連携し、相続登記を含む売却準備を一括で支援しています。戸籍の取得、遺産分割協議書の作成、登記申請の書類整備など、複雑な作業をスムーズに進める体制を整えております。
空き家のままにすると固定資産税の軽減措置が失われる
相続後、家を空き家にして放置していると、固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)が解除されてしまう可能性があります。これにより、土地部分の税額が最大で6倍になるケースもあり、思わぬ税負担を招きます。
空き家問題は、自治体にとっても社会問題となっており、世田谷区でも老朽空き家への指導が強化されています。売却を検討するのであれば、早めに名義変更と売却準備に取りかかることが重要です。
家屋の状態と耐震性の確認
売却前には、建物の劣化状況や耐震基準の確認が求められます。なぜなら、一定の耐震性が確保されていない場合、買主側が住宅ローンを利用できず、売却価格が大きく下がる可能性があるためです。
特に昭和56年5月以前に建築された建物は、旧耐震基準のため現行基準を満たさない可能性が高く、3,000万円控除などの特例適用にも影響します。必要に応じて耐震診断や取り壊しも検討する必要があります。
遺産分割が未了のまま売却を進めるリスク
複数の相続人がいる場合、遺産分割協議が完了していなければ売却はできません。名義が共有状態のままだと、全員の同意が必要になり、ひとりでも反対すれば売却できないのです。
また、売却後の代金分配を巡ってトラブルに発展するケースも多く、家族間の関係に亀裂を生む原因にもなりかねません。
売却タイミングと税制改正の影響
税制は毎年変化しており、相続税や譲渡所得税に関わる制度が見直されることで、売却のタイミングによって支払う税額が大きく変動する可能性があります。
また、インフレや地価上昇の影響で譲渡所得が増えると、税金も比例して重くなるため、売却益が高くても「手元に残る金額が少ない」事態にもなりかねません。
一方で、適切な節税対策を講じれば、数百万円単位で納税額を抑えることも可能です。齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、最新の税制動向を踏まえ、お客様ごとに最も有利な売却スケジュールと戦略を提案しております。
相続した家を売却する際の税金の節税対策と活用事例

節税の鍵は「タイミング」と「特例の活用」
相続した家を売却する際の税金を抑えるための最大のポイントは、売却のタイミングと各種税制特例の適用有無です。特に取得費加算の特例や空き家に係る3,000万円控除は、要件を満たせば大きな節税効果が得られますが、売却の時期や手続きの順序を間違えると、適用されなくなってしまいます。
たとえば、「取得費加算の特例」は、相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合にしか使えません。また、「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除」は、耐震性や居住実績などの条件をクリアして初めて認められます。
つまり、これらの特例は知っているだけでは不十分で、正しく準備し実行することで初めて税制メリットを受けられるのです。齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、税務と法務、不動産実務を横断した専門チームによる最適な節税戦略を提案しています。
不動産会社だけでは不十分な理由
相続不動産の売却を進める際、多くの方が最初に不動産会社へ相談されます。もちろん販売活動においては有効ですが、不動産会社は税務や登記、相続法務の専門家ではないため、税金の具体的なアドバイスや申告サポートは基本的に行えません。
結果として、「売却後に高額な税金が発生して初めて問題に気づく」といったケースが後を絶ちません。齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、売却前に税負担を明確化し、将来のトラブルを未然に防ぐ対応が可能です。
不動産の評価と相続税との整合性
相続時に支払った相続税と、売却時に申告する譲渡所得には密接な関係があります。相続税評価額が高すぎた場合、売却時に思ったほど利益が出なかったという状況が生じ、結果として税負担だけが重くなることもあります。
このような不整合を避けるには、相続開始時点での土地・建物の適正評価が重要です。齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、不動産鑑定士と連携した精度の高い相続税評価と売却時の譲渡益の整合性の検証を行い、納税額の最適化を図ります。
資産運用と合わせた売却戦略
相続した家をそのまま売却するだけでなく、一部を貸す、法人化して保有する、買い替えるといった選択肢も視野に入れると、税金を抑えつつ資産を活用できる可能性があります。
たとえば、売却益をもとに他の不動産に買い替えることで、譲渡課税を先延ばしにする「特定の買換え特例」の適用が検討できるケースもあります。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、売却だけでなく、保有・再投資・法人化までを視野に入れた包括的な戦略設計を行っています。税負担を抑えると同時に、資産全体の最適化を目指すお手伝いが可能です。
実際の事例に学ぶ成功パターン
実際に当事務所で支援した事例をご紹介します。
ご相談者は、東京都世田谷区にある築40年の一戸建て住宅を相続されました。相続税を支払ったあと、売却を希望されていましたが、当初は不動産会社から「売れば高く売れる」と勧められたまま進めようとしていました。
しかし、当事務所にご相談いただいたことで、
- 取得費加算の特例の期限が迫っていることを把握
- 被相続人の居住実績と耐震基準を満たしていたため、3,000万円控除の対象であると確認
- 築年数の関係で取得費が不明だったため、概算取得費よりも有利な評価額を再検証し、譲渡益を圧縮
- 相続時の評価と売却価格の差額に注意し、納税額を試算
以上のステップを経て、結果的に当初予想されていた納税額よりも約470万円の節税に成功しました。
このように、相続した家を売却する際の税金の対応には、単なる計算ではなく、制度の正しい理解と戦略的な実行が求められます。齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、こうした複雑な要素を一つずつ丁寧に整理し、お客様と一緒に最善策を導き出しています。
相続した家を売却する際の税金に関する法改正と今後の対策

相続登記の義務化とその影響
2024年4月から施行された相続登記の義務化は、これまで後回しにされがちだった「相続した不動産の名義変更」を法的義務にしたものです。相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
これにより、名義変更をせずに空き家を放置していたり、売却を進めようとしていたものの相続人間で合意が得られず手続きが滞っていたようなケースも、速やかな対応が求められるようになりました。
加えて、相続登記が未了のままでは売却ができないため、家を売却するための第一歩は「相続登記」であることを今一度意識する必要があります。齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、司法書士と連携し、登記義務化対応のサポートやスケジュール管理、必要書類の収集支援を一括して対応しています。
税制特例の改正ポイント
ここ数年、相続や譲渡に関連する税制特例も次々に改正されています。たとえば、取得費加算の特例については、相続税の加算対象金額や適用要件が見直されており、これまで以上に事前の確認と戦略的活用が求められるようになりました。
また、空き家に係る3,000万円控除についても、「耐震基準の証明」や「一定期間内の売却」など、条件が厳格化される傾向にあります。特例に頼る前提ではなく、税負担を前提にしたシミュレーションを事前に行うことが必須です。
生前対策と贈与の使い方
将来的に家を相続させる予定がある場合には、生前贈与も含めた資産移転の検討が効果的です。特に、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税贈与といった制度をうまく活用すれば、相続時の税負担を分散・軽減できる可能性があります。
ただし、贈与には贈与税が発生するケースもあり、贈与と相続のバランスを見ながら最も効果的なタイミングを選ぶことが重要です。齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、贈与・相続を一体として捉えた資産承継計画を提案しております。
複数不動産を保有している場合の注意点
相続で家だけでなく、複数の不動産を同時に引き継ぐケースでは、それぞれの売却順序や保有戦略が重要になります。たとえば、先に売却する不動産の利益が大きすぎると、他の物件の損益通算ができず税負担が重くなることもあります。
また、保有する物件によっては賃貸に出す、法人で管理するなど多様な運用方法も検討可能です。齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、物件ごとの評価と将来の出口戦略を設計することで、トータルでの最適化を実現しています。
今後に向けた相続資産の守り方
今後は少子高齢化の進展とともに、相続によって不動産を引き継ぐケースが急増すると予測されています。それに伴い、売却をめぐるトラブルや税金トラブルもより多くなる可能性があります。
このような時代の中で、ご家族の大切な資産を守るには、「単に売却する」「節税だけを考える」といった一面的な判断ではなく、総合的な視点での戦略構築が不可欠です。遺言の有無、家族の希望、資産の構成、老後資金、相続税・譲渡税の計算、地域性など、複数の要素をバランスよく整理してこそ、初めて「後悔のない資産承継」が実現します。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、世田谷区という都市型住宅地の特性を踏まえながら、お客様の背景に寄り添った提案を行っております。相続・売却・税金という一連のプロセスを「点」で終わらせず、「線」でつなぎ、「面」としてお客様の人生と家族を支える──それが、私たちの使命です。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所が提供する安心の相続サポート

税金と法律を横断する総合支援体制
相続した家を売却する際の税金というテーマには、税金だけでなく登記、法律、不動産の知識が必要不可欠です。そのため、どれか一つの専門家に任せるだけでは、対応しきれないリスクや抜け漏れが生じることもあります。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、税理士・公認会計士の専門知識を中心に、司法書士・弁護士・不動産業者との連携ネットワークを構築。お客様のご相談内容に応じて適切なパートナーと協業しながら、一貫した相続サポートを実現しています。
たとえば、相続登記が必要な場合は提携司法書士が登記手続きを担当し、売却に進む場合は提携不動産会社が適正価格での査定を実施します。税務申告はもちろん、申告後の税務調査への対応まで、ワンストップで安心をお届けできる体制を整えております。
東京都世田谷区に根差した地域密着の実績
東京都世田谷区は、都内でも地価が高く住宅需要が安定しているエリアです。一戸建てやマンションなどの相続が多く発生し、相続後の売却も活発な地域といえます。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所は、世田谷区の不動産事情と税務の特性を深く理解している地域密着型の事務所として、多くの相続案件を手がけてまいりました。
世田谷エリアで家を相続された方には、路線価・固定資産評価・市場価格を的確に捉えたうえでの売却シミュレーションや節税提案が可能です。地域特有の地目や接道条件にも配慮したアドバイスを提供し、お客様にとって納得できる選択肢をご提案いたします。
お客様の「不安」を「納得」に変える面談スタイル
相続や家の売却は、初めて経験される方がほとんどです。そのため、「何を聞けばいいかわからない」「間違った判断をしそうで怖い」という声も多く聞かれます。
そこで当事務所では、一方的な説明ではなく「お客様が抱えている悩みや背景」を丁寧に伺いながら、状況に即したアドバイスを提供するスタイルを重視しています。
初回相談では、現状の財産状況やご家族構成、売却のご希望などをお伺いし、必要な手続きの流れと発生しうる税金、適用可能な特例、想定されるスケジュールなどを、図解や資料を交えて分かりやすくご説明します。
「売る」だけでなく「守る」「残す」までを視野に
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所の相続サポートは、単に「売却して終わり」ではありません。大切な財産をいかに守り、次世代へどう引き継いでいくかまでを見据えたサポートを行っています。
たとえば、売却で得た資金の活用方法として、生命保険や資産管理会社の設立、再投資による資産形成などを組み合わせたご提案も可能です。相続税対策と譲渡所得税対策をトータルで考えながら、お客様の人生設計に合ったプランを共に描いていきます。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所が選ばれる理由
お客様が当事務所を選んでくださる理由には、次のようなポイントがあります。
- 相続・資産承継の実績が豊富:これまでに多数の相続不動産売却案件を手がけており、確かな経験があります。
- 税務申告+登記+不動産+法律まで対応可能な総合力:お客様が複数の専門家を探す必要がありません。
- 初回相談から代表税理士が直接対応:ご相談から実行までブレのない安心感を提供しています。
- 地域密着でスピード対応が可能:世田谷区周辺の物件評価や税務対応に熟知しているため、迅速なサポートが可能です。
- 「専門用語を使わない」わかりやすさ重視の説明:お客様が納得できるまで、何度でも丁寧にご説明いたします。
このように、齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、税金・法律・家族の未来をトータルで考える相続パートナーとして、お客様の声に寄り添いながら実務を進めています。
Q&A:相続した家を売却する際の税金に関するよくあるご質問

Q1. 相続した家を売ると、必ず税金がかかるのですか?
→ ケースによって異なりますが、譲渡所得が発生する場合は所得税・住民税がかかります。ただし、「取得費加算の特例」や「3,000万円特別控除」などの制度を利用できれば、実際に支払う税金を大幅に減らせることもあります。
Q2. 被相続人が長く住んでいた家を売るときに使える優遇制度はありますか?
→ はい。「被相続人居住用財産の3,000万円特別控除」が該当する可能性があります。要件を満たせば、譲渡所得から3,000万円を控除できます。ただし、耐震性や売却時期などに条件があるため注意が必要です。
Q3. 相続登記をしていなくても家は売れますか?
→ いいえ。売却するには必ず相続登記(名義変更)が必要です。登記が完了していないと、不動産の所有者として売買契約を結ぶことができません。2024年からは義務化もされているため、早めの対応が大切です。
Q4. 相続税を払ったのに、売却でも税金がかかるのはなぜですか?
→ 相続税と譲渡所得税は性質が異なる税金で、それぞれ別に課税されます。相続税は相続時にかかる税、譲渡所得税は「売って利益が出たとき」にかかる税金です。ただし、相続税を取得費に加算できる特例により、一定の調整が可能です。
Q5. 被相続人が購入したときの「取得費」がわかりません。どうしたら?
→ 取得費が不明な場合は、「概算取得費(売却価格の5%)」を適用して計算することが認められています。ただし、古い資料や契約書などを探し出せば、実際の取得費で申告できる場合もあり、結果として税金が安くなる可能性があります。
Q6. 売却で得たお金を、他の資産に再投資すれば節税になりますか?
→ 条件によっては可能です。たとえば、特定の買換え特例や法人設立による管理スキームの構築など、再投資型の戦略で課税を繰り延べたり、所得分散を図る方法があります。事前にしっかりと計画を立てることが重要です。
Q7. 売却の手続きは不動産会社に任せればいいですか?
→ 売却活動そのものは不動産会社が行いますが、税金の計算や申告、特例適用の判断は税理士の専門分野です。とくに譲渡所得の申告には高い専門性が求められるため、不動産と税務の両方に強い専門家への相談が不可欠です。
まとめ

相続した家を売却する際には、複数の税金や法的手続きを正確に理解し、順序立てて対応することがとても重要です。特に「相続した家を売却する際の税金」の問題は、相続税・譲渡所得税・固定資産税など、複数の税法が絡み合い、専門性が極めて高い領域となります。
相続登記が未了では売却ができず、売却後に高額な税金が発生する可能性もあるため、事前のシミュレーションと特例の適用判断が欠かせません。また、被相続人の居住用財産であれば3,000万円特別控除や取得費加算の特例といった制度を活用することで、適切に税負担を軽減することが可能です。
しかし、これらの制度はどれも適用条件が厳密に定められており、タイミングや申告方法を誤ると適用を受けられないリスクもあります。さらに、売却益を新たな資産形成や老後資金として活用する際にも、税制を理解した戦略的活用が求められます。
だからこそ、相続・不動産・税金を総合的に把握できる専門家のサポートが不可欠です。
東京都世田谷区に拠点を構える齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、相続や家の売却に関するすべてのプロセスを、ワンストップで誠実に対応しております。
- 税理士による譲渡所得の試算と申告支援
- 司法書士との連携による相続登記の代行
- 不動産業者と連携した適正価格での売却サポート
- 法律面・契約面でのトラブル予防のアドバイス
- 節税と資産活用を組み合わせた提案
お客様の「思いをかたちにし、ご家族の未来を守ること」が私たちの使命です。相続した家をどう活かすか、どう売却すべきか悩んでおられる方は、どうぞ一度、齋藤久誠公認会計士・税理士事務所へお気軽にご相談ください。
初回のご相談は丁寧に、そして分かりやすく対応いたします。

(東京税理士会玉川支部所属(登録番号:139151号)
FAQ
よくあるご質問
- 電話・メールでの税務相談は可能ですか?
- 当事務所の方針としまして、ご相談の際には、直接お会いしてお話させていただいております。ただし、場合によっては、お電話にて相談を承る場合もあります。詳しくは、一度お電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 相談に行く際、事前に準備しておくべきことはありますか
- 初回面談はお客様のご相談事項をお伺いすることが中心です。ご相談事項に関連する資料をご準備ください。
- 費用はいくらかかりますか?
- お支払いいただく費用はご依頼事項により異なります。ご依頼いただく前にお見積書を作成させていただきますのでご依頼ください。
- 駐車場はありますか?
- 当事務所は専用駐車場を用意しておりません。近隣の駐車場をご利用いただくか公共交通機関でのご来訪をお願いいたします。
- 予約なしで相談できますか?
- 当事務所は完全予約制とさせていただいております。ご相談をご希望の際は、事前に電話またはメールでのお問合せをお願い致します。
information
事務所情報

- 住所
-
〒158-0094
東京都世田谷区玉川3-11-1柳小路東角3階310
- tel
- 050-3639-1594
- 営業時間
-
平日 9:00〜18:00 / 土曜 9:00〜12:00
当社は完全予約制となっております。
- メールアドレス
- saito@cpatax-office.com
- 定休日
- 日、 祝日
- 最寄り駅
- 東急田園都市線・大井町線『二子玉川』駅 徒歩3分