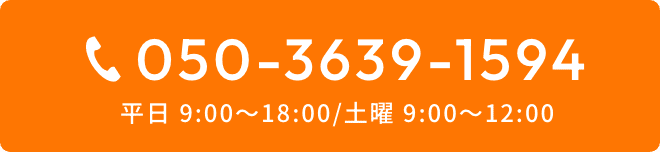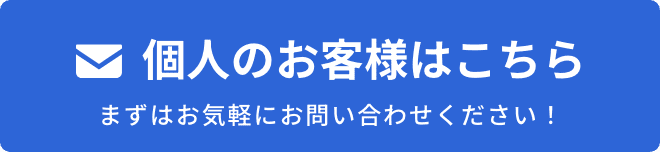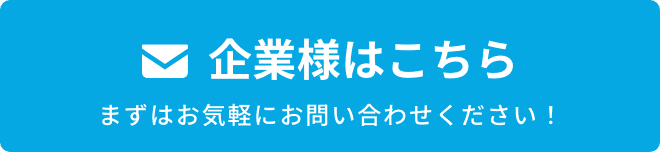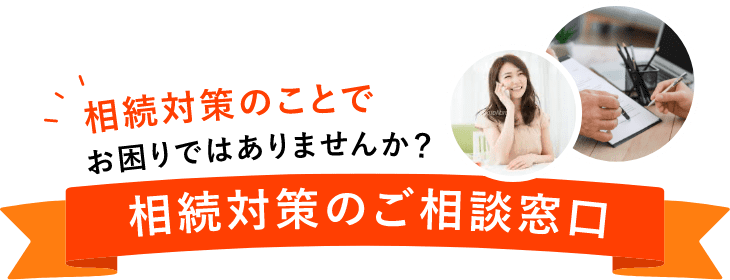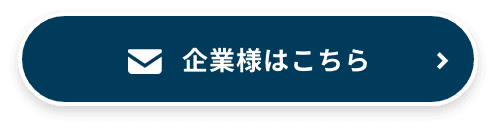ブログ
相続対策に生命保険は本当におすすめ?齋藤久誠公認会計士・税理士事務所の専門解説【東京都世田谷区】

相続対策という言葉を聞くと、多くの方が「税金対策」や「不動産の分割」を思い浮かべるかもしれません。確かにそれらも重要ですが、実は見落とされがちで、かつ非常に効果的な手段のひとつが生命保険の活用です。特に、納税資金の確保や相続人間のトラブル回避といった観点から、生命保険は非常にバランスの取れた方法としておすすめできる選択肢となっています。
しかし、「相続対策におすすめの生命保険」と一言でいっても、終身保険・定期保険・養老保険・変額保険など種類は多岐にわたります。また、加入者・契約者・受取人といった登場人物の関係性によっても、税務上の取り扱いやリスクが大きく異なるため、専門的な知識がなければ本来の効果を最大限に引き出すことは困難です。
当事務所でのご相談でも、「保険会社の営業担当にすすめられて加入したが、相続対策として本当に適しているのか不安」「保険金の非課税枠についてよく分かっていなかった」「受取人を配偶者にしたけど、それで良かったのか確認したい」といった声を多くいただきます。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所(東京都世田谷区)では、こうしたお客様の不安や疑問に真摯に向き合い、生命保険を含めた総合的な相続対策をワンストップでご提案しています。税理士・司法書士・弁護士・保険会社・不動産業者と連携し、それぞれの専門領域をまたいだご支援が可能です。
本記事では、「相続対策における生命保険のおすすめポイントとは何か」「どのような種類の保険をどう活用すればよいのか」「注意すべき落とし穴や設計ミスとは何か」など、具体的な事例と共にわかりやすく解説してまいります。
相続や生前対策を“なんとなく不安”に感じている方が、“知識・理解・納得”できるように。 そして、「じゃあ、齋藤久誠公認会計士・税理士事務所に相談してみようかな」と思っていただけるように、専門的かつ誠実な内容を心がけてお届けいたします。
目次
相続対策における生命保険の役割とは

なぜ生命保険が相続対策におすすめされるのか
生命保険は、他の財産とは異なる“即時性と確実性”を備えた特別な相続対策ツールです。
例えば、現金や不動産、有価証券などの資産は、分割や換金に時間がかかる場合がありますが、生命保険は被保険者の死亡によって迅速に保険金として受取人に支払われます。これにより、相続発生直後の急な資金ニーズにも対応できる点で、非常に優れた相続対策の手段としておすすめされています。
さらに、生命保険は契約内容次第で受取人を自由に指定することができるため、相続財産とは別枠で特定の人へ確実に資金を渡すことができます。これにより、「長年介護してくれた子に多めに財産を渡したい」といった被相続人の想いを実現する手段としても有効です。
保険金の非課税枠を活用するメリット
相続対策において生命保険が注目される最大の理由のひとつが、「500万円×法定相続人」の非課税枠の存在です。
たとえば、配偶者と子2人が相続人であれば、500万円×3人=1,500万円までの生命保険金が相続税の課税対象から除外されます。これは、他の財産にはない生命保険特有の優遇措置であり、現金のまま保有しているよりも有利に働くケースが多いです。
特に、現金資産が少ない方にとっては、生命保険を活用してこの非課税枠を戦略的に使うことで、相続税の圧縮と納税資金の確保の両立が可能となります。これはまさに、「相続対策において生命保険がおすすめされる根拠」のひとつといえるでしょう。
保険は納税資金の確保手段としても有効
生命保険の最大の強みは、相続税の納税資金を“確実に”用意できる点です。
相続税は、原則として相続発生から10か月以内に現金で納付する必要があります。不動産が主な遺産である場合などは、「資産はあるけど現金がない」という事態になりがちです。
その点、生命保険であれば契約時に目的を“納税資金の確保”と位置づけ、必要額を逆算して設定しておくことで、相続人が困ることなくスムーズに納税できる状況を作り出すことが可能です。これは、実際に相続トラブルが発生する前に準備しておくべき、極めて実用的な対策です。
相続分割の調整機能としての役割
生命保険は、相続財産の“分けにくさ”を補う調整ツールとしても効果を発揮します。
たとえば、不動産しか遺産がない場合、相続人全員で公平に分けるのが困難です。1人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払うといった方法が取られますが、代償金を準備できないと分割協議が行き詰まってしまいます。
そこで、生命保険を活用すれば、受取人を他の相続人に設定することで“分配の調整”が可能となり、結果として相続トラブルの回避につながります。 不動産の代わりに保険金を受け取ることで、納得度の高い遺産分割を実現できるというわけです。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所の実務に基づくポイント
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、生命保険を活用した相続対策の実務経験が豊富にあります。
単に「生命保険がおすすめですよ」と案内するだけでなく、契約者・被保険者・受取人の関係性による課税区分、非課税枠の最大活用、二次相続対策とのバランスなど、実際に“効果の出る設計”を一緒に考えることを大切にしています。
また、東京都世田谷区を中心に、地元の保険代理店・弁護士・司法書士との連携体制を整え、お客様のご希望に合った保険プランを中立的な立場でご提案しています。「保険の勧誘」ではなく、「資産承継全体を見据えた最適な保険活用のご提案」をすることが、私たちの使命だと考えております。
相続対策で検討すべき生命保険の種類と特徴

終身保険の基本と相続との相性
終身保険は、相続対策において最も基本かつおすすめできる保険のひとつです。
被保険者が亡くなった時点で、必ず保険金が支払われるタイプのため、「いつかの時点で確実に現金が入る」という性質を持ちます。この「確実性」こそが、相続対策において終身保険が重宝される最大の理由です。
さらに、保険金受取人を特定の相続人に設定しておくことで、納税資金の確保や相続分の調整にも役立ちます。 また、保険金には非課税枠があるため、他の資産と比較して税制上も有利です。こうした理由から、齋藤久誠公認会計士・税理士事務所でも終身保険を用いた設計を数多く行っており、実務上の相性が非常に良い商品といえます。
定期保険の使いどころと注意点
定期保険は、一定期間に限って保障が続くタイプの保険です。
掛け捨てであるため保険料が比較的安く、特定のタイミング(たとえば子どもが独立するまで)で大きな保障を持ちたい場合に適しています。
相続対策の観点では、「死亡時に必ず保険金が支払われる」という確実性に欠けるため、あくまで補助的な位置づけになります。 たとえば、高齢の親が加入するには期間の制限があり、保険料も割高になるため、相続目的での加入は慎重に検討すべきといえるでしょう。
養老保険の特性と活用事例
養老保険は「保障」と「貯蓄」が一体化した商品で、満期まで生存すれば満期保険金を受け取ることができます。
そのため、相続対策と同時に老後資金としても活用できる柔軟性が魅力です。
ただし、保険料が比較的高額になるため、資金に余裕がある方向けの設計になります。 相続税の節税を目的とした場合、満期前に死亡したときのみ保険金が相続財産として扱われますが、生前に満期保険金を受け取ると贈与の問題が生じる可能性もあります。契約内容と支払時期の調整が極めて重要なポイントとなります。
変額保険・外貨建て保険のリスク
変額保険や外貨建て保険は、投資の要素を含んだ商品であり、相続対策においては慎重な判断が必要です。
相続人にとって、受け取る保険金額が確定していないという不確実性は大きなストレスになることがあります。また、為替リスクや市場リスクの影響を受けるため、「資産を確実に残す」という相続本来の目的にはやや不向きといえるでしょう。
もちろん、運用が成功すれば大きなリターンも期待できますが、相続対策としては“保険本来の役割”を果たしづらくなるリスクがあることを念頭に置く必要があります。齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、これらの商品についても第三者的視点からリスク評価を行い、ご相談者様にとって本当に必要な保険かを丁寧にご説明します。
ケース別におすすめできる保険の選び方
相続対策において「どの保険が良いか」は、その方の家族構成・財産構成・将来の希望によってまったく異なります。
たとえば、
- 高齢の親が現金で財産を残したくない場合 → 終身保険で非課税枠を活用
- 配偶者の生活資金を確保したい場合 → 養老保険や終身保険
- 相続人の数が多く公平な分配が必要な場合 → 終身保険+受取人分散
- 納税資金を確実に用意したい場合 → 高額終身保険の設計
このように、目的に応じた商品選びと設計が相続対策の生命保険には求められます。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、お客様の目的と家族関係をしっかりとヒアリングし、本当におすすめできる生命保険の種類と設計内容をご提案しています。
相続対策で生命保険を活用する際の注意点

保険金の受取人指定におけるリスク
生命保険の大きな特徴であり利点でもあるのが「受取人を指定できる」ことですが、これが逆にトラブルの火種になるケースもあります。
たとえば、長男だけを保険金受取人にしていた場合、他の相続人から「不公平だ」「生前に聞いていなかった」として不満が噴出することも少なくありません。生命保険金は「受取人固有の財産」として相続財産とは別扱いになりますが、遺産分割協議の際に感情的な対立を引き起こすことが多い項目です。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、こうしたケースも見据え、相続人間の納得を得られるように保険金の受取人設計や遺言との整合性についてアドバイスしています。
生命保険信託との違いと使い分け
近年注目されている「生命保険信託」は、保険金を信託化することで、より柔軟な相続設計が可能になる仕組みです。
通常の生命保険では、受取人が一括で保険金を受け取りますが、生命保険信託を利用すれば、「毎月〇万円ずつ受け取る」「特定の条件で支払う」など分割支払い・制限付きの運用が可能です。
たとえば、高齢の配偶者が一括の大金を管理するのが不安な場合、信託を通じて計画的に資金を受け取る設計にすることで安心感が高まります。信託は設計と管理が複雑になるため、専門家との連携が不可欠であり、齋藤久誠公認会計士・税理士事務所でも弁護士・信託会社と連携し、最適なスキーム構築を支援しています。
二次相続に対応できる設計とは
一次相続(たとえば父→母)だけでなく、二次相続(母→子)までを見据えた設計を行うことが、実はとても重要です。
生命保険で配偶者が全額を受け取ってしまうと、二次相続時に相続税の軽減措置が使えず、かえって税負担が大きくなることがあります。
たとえば、終身保険を配偶者ではなく子どもに分けて設定する、あるいは保険金を信託にして複数のタイミングで渡すなど、世代をまたいだ視点で設計することで相続全体の最適化が図れます。
当事務所では、一次・二次相続をシミュレーションし、「今だけでなく将来を見据えた生命保険活用」ができるようなご提案を心がけています。
保険料支払者と契約者の一致に注意
生命保険の契約関係者(契約者・被保険者・受取人)の組み合わせによって、課税関係が大きく異なることをご存じでしょうか。
例えば、契約者が父、被保険者も父、受取人が子であれば「相続税」の対象になりますが、契約者が子で保険料も子が負担していると、「贈与税」の課税対象になるケースもあります。
このように、保険の契約形態を誤ると、予期しない高額な課税を受ける可能性があるため、契約時の設計は慎重に行うべきです。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、税法に基づく正しい契約形態を設計し、贈与税と相続税のリスクを最小限に抑えるご提案を行っています。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所が行うチェックポイント
当事務所では、生命保険を活用する前に以下のようなチェック項目をもとにお客様と一緒に内容を確認します。
- 目的が納税資金確保か、相続分配か、生活保障か明確になっているか
- 契約形態(契約者・被保険者・受取人)の課税区分に誤りがないか
- 一次相続・二次相続を見据えた長期設計になっているか
- 他の財産とのバランスがとれているか
- 他の相続人との調整が取れる設計になっているか
これらの点を慎重に検討しながら、専門家として“本当におすすめできる生命保険の使い方”を丁寧にお伝えしています。
生命保険は万能ではありませんが、正しく使えば相続対策において非常に強力なツールとなります。
生命保険だけに頼らない相続対策の考え方

不動産・信託・現金の活用と組み合わせ
生命保険は相続対策において非常に有効な手段ですが、それだけで万全というわけではありません。
なぜなら、家族構成や財産の種類、将来のライフプランによって必要な対策は大きく変わるからです。
たとえば、不動産を多く保有している方であれば、生命保険だけではなく、不動産の評価・売却・管理計画までをセットで考える必要があります。 また、認知症リスクを踏まえるなら家族信託を用いて財産管理権限を委託することも有効です。
さらに、現金・預金を適度に保有しておくことは、納税や遺産分割をスムーズに進めるためにも重要です。齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、こうした各種資産の特性を踏まえたトータル設計を重視し、生命保険と他資産の最適な組み合わせを提案しています。
保険と遺言・家族信託の併用事例
生命保険単体では対応しきれない“想いの継承”には、遺言や家族信託を組み合わせることで真価を発揮します。
たとえば、長女には現金を、長男には不動産を相続させたいという場合、生命保険で現金を確保し、遺言で不動産の指定相続を行うことで円満な遺産分割が可能になります。
また、認知症などで判断力を失った後に発生するトラブルを未然に防ぐには、生命保険契約を信託化しておくことで、柔軟な管理と資金分配が可能になります。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、保険・信託・遺言を一体的に活用する事例設計にも豊富な経験があり、複数の専門家ネットワークを活用しながら、実行支援を行っています。
税務上のバランスを取る資産構成
税金は、相続対策において“最後に一番影響を与える要素”です。
生命保険で非課税枠を活用するのは有効ですが、そればかりに偏ってしまうと、他の資産との整合性が崩れ、結果的に相続税が増えてしまうケースもあります。
たとえば、不動産の評価減と保険金の非課税を同時に活かす設計や、生前贈与による課税回避、配偶者控除の最大活用など、税制に基づいた全体最適化が必要です。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、相続税専門のノウハウをもとに、「保険だけでなく、税務に強い相続対策」の設計を大切にしています。税理士であるからこそできる、数字に基づいた提案力が当事務所の強みです。
実際に起きたトラブル事例から学ぶこと
「保険に入っていたのに相続でもめた」という話は決して珍しくありません。
あるご家庭では、保険金の受取人が長男だけに設定されていたため、次男・長女が「不公平だ」として争いになり、遺産分割協議が泥沼化した事例がありました。
また、他の事例では、契約者と保険料支払者が異なっていたため、税務署から贈与税の申告漏れを指摘されたケースもあります。こうしたトラブルは、「保険だけで対策した」ゆえに起きたものであり、やはり“全体設計の重要性”が問われる典型例といえます。
当事務所では、こうした過去の実例から学び、再発防止のためのチェック体制を整えています。お客様が安心して生命保険を活用できるよう、契約前後のサポート体制も万全です。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所の総合支援体制
当事務所では、生命保険をはじめとした相続対策をワンストップで支援しています。
税理士の専門性だけでなく、司法書士・弁護士・不動産会社・保険代理店と連携し、お客様の財産状況と家族関係に合わせて、必要な手段を中立の立場からご提案いたします。
また、東京都世田谷区を拠点に地域密着で活動しており、相続に強い専門家として多数の実績があります。生命保険の提案に偏ることなく、お客様の“思い”を最優先にした総合的なアドバイスが可能です。
「相続対策って何から始めればいいかわからない」という方でも、まずは生命保険の検討をきっかけに、当事務所にご相談いただければ、最適な対策への第一歩を一緒に歩んでいけると自負しております。
東京都世田谷区で相続対策を相談するなら

齋藤久誠公認会計士・税理士事務所の理念
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所は、「お客様の“思い”に寄り添い、家族の未来を守る相続対策」を信念としています。
東京都世田谷区という地域に根差しながら、資産の大小に関係なく、一人ひとりの状況に最もふさわしい生前対策・相続対策を提案することを大切にしています。
単なる税務申告だけでなく、「家族がもめないための仕組み」「納得して分けられる財産設計」「税金を減らしながら生活も守る方法」など、“数字と心”の両方に向き合った提案を行うことが当事務所の理念です。
生命保険の活用もその一環であり、「おすすめの保険」を紹介するのではなく、“その方に本当に必要な保険かどうか”を冷静に検証し、専門家としてアドバイスいたします。
ご相談から解決までの流れ
初めてのご相談でもご安心ください。齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、明確なステップでサポートいたします。
- 無料の初回面談(またはオンライン相談)
お客様のご状況、ご希望、ご家族構成、資産内容などを丁寧にヒアリングします。 - 資産分析とリスク診断
現状の相続税シミュレーション、生命保険の内容確認、遺言・信託の有無などをチェック。 - 対策提案と専門家連携
税理士としての提案だけでなく、司法書士・弁護士・保険代理店などと連携し、総合的な対策案を作成します。 - 実行支援・保険設計
必要に応じて保険契約の見直し、契約変更、信託設定、遺言作成などを支援いたします。 - 定期的な見直し・継続フォロー
ご家族の状況や法律・税制の変化に応じて、アフターフォローも徹底しています。
このように、相談から実行までを“ワンストップ”で対応できる体制が整っているのが当事務所の強みです。
地域に密着した専門ネットワーク
東京都世田谷区という地域特性に応じた専門家ネットワークがあることも、当事務所の大きな価値のひとつです。
相続では、税理士だけで解決できない場面もあります。たとえば、土地の名義変更は司法書士、不動産売却は不動産会社、保険設計は信頼できる代理店など、多岐にわたる連携が必要です。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、世田谷区・渋谷区・目黒区・杉並区など地域に精通した専門家たちとの実績ある連携体制を構築しており、迅速かつ的確な対応が可能です。
「信頼できる専門家を一から探すのが不安…」という方も、窓口は当事務所ひとつで完結します。
よくあるお悩みに対する対応実績
当事務所には、以下のようなお悩みで多くのご相談が寄せられています。
- 「子どもたちに平等に財産を渡したいが、不動産と現金のバランスが悪い」
- 「保険に入っているが、相続対策になっているか不安」
- 「認知症になった後、相続手続きが複雑にならないか心配」
- 「遺言はあるけど、生命保険との関係がわからない」
- 「老後資金と相続のバランスをどう考えるべきか?」
こうした声に対して、税務・法律・資産運用の観点から、実務に即した対応を行っております。
相続対策は一つの方法だけではなく、複数の対策を組み合わせてこそ真の効果が発揮されると私たちは考えています。
相続対策と生命保険を正しく繋ぐために
相続対策として生命保険を活用するには、「正しい知識」と「目的に合った設計」が不可欠です。
生命保険は、遺産分割、納税資金、家族間の調整といった複数の目的に対応できる優れたツールですが、誤った活用をしてしまうと、かえって相続トラブルや税務リスクの原因になりかねません。
だからこそ、税務・法律・実務をすべて見通した上で“何を・どのように・誰に”残すのかを考える必要があります。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、お客様とそのご家族の未来を守るために、一人ひとりに最適な生命保険の活用方法をオーダーメイドでご提案しています。
「生命保険を使って相続対策をしたい」「本当にこの保険でいいのか不安」と感じたら、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
Q&A:相続対策×生命保険についてよくあるご質問

Q1. 相続対策として生命保険は本当におすすめですか?
はい、生命保険は相続対策の中でも特におすすめできる手段の一つです。
生命保険には「納税資金の確保」「遺産分割の調整」「非課税枠の活用」という3つの大きな利点があります。特に、現金で遺産を残すのが難しい場合においても、確実に“使えるお金”を相続人に渡すことができる点が大きな魅力です。
Q2. 非課税になるのはどのくらいまでですか?
法定相続人1人につき500万円までが非課税枠となります。
たとえば、配偶者と子ども2人の場合、最大で1,500万円までの生命保険金が相続税の課税対象から除外されます。 これは現金や不動産にはない特典であり、相続税の軽減手段として非常に有効です。
Q3. どの種類の生命保険が相続対策に向いていますか?
一般的には終身保険がもっとも相続対策に向いています。
なぜなら、終身保険は被保険者が亡くなったときに必ず保険金が支払われるため、確実性と納税資金の確保に適しているからです。契約内容や目的に応じて定期保険や養老保険、信託型保険なども使い分けるとよいでしょう。
Q4. 保険金の受取人は誰にすべきですか?
目的によって適切な受取人は異なります。
納税資金の確保を重視するなら相続人全体のバランスを見て設定するべきですし、生活保障を目的とするなら配偶者を受取人にするのが一般的です。 ただし、指定の偏りがトラブルを生むこともあるため、専門家と相談しながら設計するのが安心です。
Q5. 保険会社に相談すればよいのでしょうか?
保険会社は商品の提案には強いですが、税務や遺産分割の全体像まではカバーできません。
そのため、税理士や司法書士などと連携できる専門事務所に相談することが重要です。 齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、商品選定だけでなく、契約形態・相続人の調整・税金計算まで総合的にサポートしております。
Q6. 契約者や保険料の支払い者が違うと問題ですか?
はい、税金の課税対象が変わるため注意が必要です。
たとえば、契約者と被保険者が父で受取人が子の場合は相続税がかかりますが、契約者が子で保険料も子が負担していると贈与税になる場合もあります。 正しい契約設計を行わないと想定外の課税リスクが発生します。
Q7. 生命保険と遺言・信託は併用できますか?
はい、むしろ併用することで相続対策がより効果的になります。
生命保険だけではカバーしきれない部分を遺言で補完したり、家族信託で柔軟な支払い方法を設計したりすることで、家族にとってより安心できる仕組みが完成します。当事務所ではそれぞれの特性を活かした提案をしています。
まとめ

相続対策は、「財産を残す」ことと同時に、「家族の未来を守る」ための大切な準備です。
その中で、生命保険は非常に優れたツールであり、納税資金の確保、遺産分割の調整、相続税の軽減といった複数の目的に対して、シンプルで効果的な対策を実現できる手段としておすすめされています。
しかしながら、生命保険には契約形態・受取人の設定・税務処理・他の財産とのバランスなど、専門的な知識と慎重な設計が求められる側面もあります。 せっかくの生命保険も、設計を誤れば「相続トラブルの火種」や「課税リスク」になってしまうことさえあるのです。
だからこそ重要なのが、生命保険単体に頼らず、相続全体を見据えた「総合的な視点」での設計です。
遺言や家族信託、不動産、現金資産などとの連携を図ることで、よりスムーズで納得のいく相続を実現できます。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所(東京都世田谷区)では、生命保険を含むあらゆる相続対策を、税理士としての視点に加え、司法書士・弁護士・保険代理店などの信頼できる専門家とのネットワークを活かし、ワンストップでご提案しています。
「生命保険で相続対策を始めたいけど、どこに相談すればよいかわからない」
「今加入している保険が相続対策に本当に適しているか不安」
「家族に揉め事を残したくない」
こうしたお悩みや想いをお持ちの方にこそ、ぜひ一度、齋藤久誠公認会計士・税理士事務所にご相談ください。
専門的な知識と経験、そして何より“お客様の思いに寄り添う姿勢”をもって、家族の未来を支えるための最適な相続対策を一緒に考え、実行してまいります。
大切なご家族のために、今日からできる相続対策を始めてみませんか?

(東京税理士会玉川支部所属(登録番号:139151号)
FAQ
よくあるご質問
- 電話・メールでの税務相談は可能ですか?
- 当事務所の方針としまして、ご相談の際には、直接お会いしてお話させていただいております。ただし、場合によっては、お電話にて相談を承る場合もあります。詳しくは、一度お電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 相談に行く際、事前に準備しておくべきことはありますか
- 初回面談はお客様のご相談事項をお伺いすることが中心です。ご相談事項に関連する資料をご準備ください。
- 費用はいくらかかりますか?
- お支払いいただく費用はご依頼事項により異なります。ご依頼いただく前にお見積書を作成させていただきますのでご依頼ください。
- 駐車場はありますか?
- 当事務所は専用駐車場を用意しておりません。近隣の駐車場をご利用いただくか公共交通機関でのご来訪をお願いいたします。
- 予約なしで相談できますか?
- 当事務所は完全予約制とさせていただいております。ご相談をご希望の際は、事前に電話またはメールでのお問合せをお願い致します。
information
事務所情報

- 住所
-
〒158-0094
東京都世田谷区玉川3-11-1柳小路東角3階310
- tel
- 050-3639-1594
- 営業時間
-
平日 9:00〜18:00 / 土曜 9:00〜12:00
当社は完全予約制となっております。
- メールアドレス
- saito@cpatax-office.com
- 定休日
- 日、 祝日
- 最寄り駅
- 東急田園都市線・大井町線『二子玉川』駅 徒歩3分