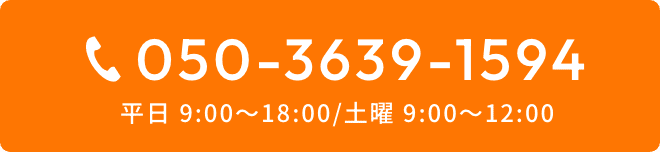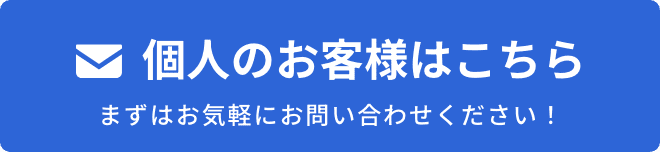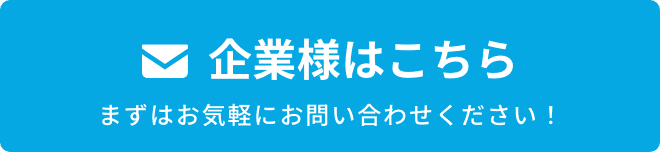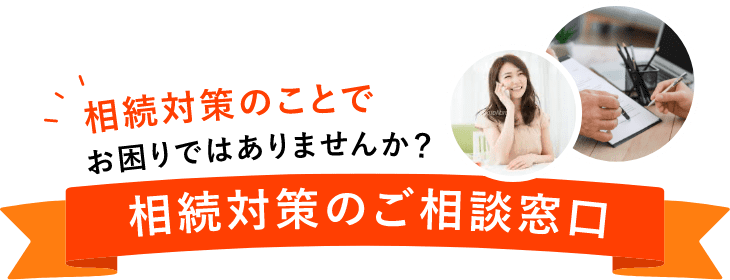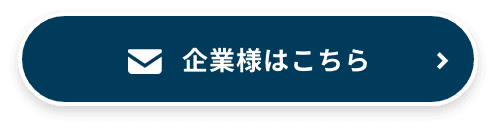ブログ
相続対策における不動産活用のデメリットとは?東京都世田谷区の齋藤久誠公認会計士・税理士事務所が徹底解説

相続対策を検討する際、多くの方がまず思い浮かべるのが不動産の活用です。不動産は現物資産として価値がわかりやすく、安定資産として代々受け継いでいけるというイメージから、生前における相続対策の手段として広く利用されています。しかしその一方で、不動産には特有のデメリットも数多く存在しており、それらを十分に理解しないまま対策を進めてしまうと、かえってご家族や相続人に大きな負担を残す結果になりかねません。
東京都世田谷区に拠点を置く齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、そうしたリスクを未然に防ぎ、お客様一人ひとりに最適な相続対策を構築することを使命としています。不動産の評価、管理、活用、売却、信託、贈与、遺言などを含む相続にまつわる課題は多岐にわたり、専門的な知識と多角的な視点が必要です。
例えば、単に「不動産を相続させることで節税ができる」といった短絡的な判断では、思わぬ税務トラブルや家族間の紛争に発展するケースも少なくありません。特に都内にある土地や建物などは資産評価額が高額になりやすく、相続税の負担や納税資金の確保が大きな問題になります。また、管理コストや賃貸経営に伴うリスクなど、所有を続けることで発生する長期的なコストも無視できません。
そこで本記事では、相続対策として不動産を活用する際に知っておくべき主なデメリットとその対応策を、事例や実務の観点も交えながら丁寧に解説いたします。「相続対策」として何が必要か、「不動産」をどう位置付けるべきか、そしてその裏に潜む「デメリット」にはどのように対処すべきか――。読者の皆様がこれらをしっかりと理解し、ご家族にとって最も良い選択ができるよう、実務家の立場からお手伝いができれば幸いです。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、税理士のみならず弁護士・司法書士・保険会社・不動産会社と連携し、すべての相続対策をワンストップで支援しています。この記事を通じて、お客様が本当に納得のいく形で財産を引き継げるよう、その第一歩を踏み出す手助けができればと考えております。
目次
不動産を活用した相続対策の現状と課題

不動産が注目される理由
相続対策において不動産が重視される背景には、いくつかの明確な理由があります。
第一に、不動産は現物資産であるため、資産価値が明確であり、代々引き継いでいける財産として捉えられています。特に東京都世田谷区のような都市部では、地価が安定しており、将来的な資産価値の上昇を見込めるため、相続対象としての人気が高い傾向があります。
第二に、不動産は相続税評価額と実勢価格との間に乖離がある場合があり、相続税を軽減できる可能性があるという期待から、節税手段としても注目されています。これが「不動産による相続対策は有効である」と言われる所以です。
不動産を使った相続対策の基本的な仕組み
不動産を活用した相続対策の基本は、“評価額の圧縮”にあります。
たとえば、現金で5,000万円の資産を持っていた場合はそのまま5,000万円が評価対象になりますが、不動産に転換した場合、借地権割合や貸家建付地の評価などが適用されることにより、評価額が数割低くなるケースもあります。
また、不動産を生前に贈与したり、賃貸不動産に転換したりすることで、より複雑かつ効果的な対策を構築することも可能です。しかしその一方で、不動産特有の管理コストや評価の不安定さが後々大きな問題となる可能性もあります。
なぜ「不動産=相続に強い」と思われているのか
多くの方が「相続には不動産が強い」と感じる理由は、メディアや専門家による紹介もありますが、やはり「目に見える形で資産を残せる安心感」が根底にあると考えられます。
また、空き地や空き家を保有している人が「どうせ持っているなら相続対策にも使えるだろう」と思うのは自然な心理です。
しかし、相続の全体像を正確に捉えずに不動産だけに依存してしまうと、思わぬデメリットを見落としてしまう危険性があります。
不動産活用による資産の偏りリスク
不動産に資産を集中させすぎることで、現金や有価証券といった流動性の高い資産が不足し、納税資金の確保が困難になるケースが実際に起きています。
また、相続人が複数いる場合、「不動産をどう分けるか」が争点になり、遺産分割トラブルに発展する事例も少なくありません。不動産は1つの物件であるため、物理的に平等に分けるのが難しく、感情的な争いが起こるリスクをはらんでいます。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所が考えるバランスある資産設計
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、「不動産だけに頼らないバランスのとれた相続対策」を提案しています。
例えば、不動産の価値を正確に評価したうえで、生命保険の活用や家族信託の設計、現金・有価証券の確保を含めたプランニングを行います。
また、不動産の管理や売却に関する助言も行い、必要に応じて不動産会社や司法書士と連携し、ワンストップで包括的な相続対策を支援いたします。お客様の「思いの実現」と、ご家族全体の将来に配慮した資産設計を目指して、東京都世田谷区から全国へ対応可能なサポート体制を整えています。
「相続対策における不動産のデメリット」とは何か

流動性リスクと現金化の難しさ
不動産の最大のデメリットのひとつが「すぐにお金に換えられない」という流動性の低さです。
現金や株式などと異なり、不動産は市場に出してから売却までに時間がかかります。さらに、売却時期や買い手の状況によっては、希望価格で売れない可能性もあります。
相続税の納税期限は、原則として相続開始後10ヶ月以内。不動産しかない相続財産の場合、納税資金の捻出が困難になり、結果として借入をして支払う、もしくは不利な条件で急いで売却するなど、相続人の負担が増すことにつながります。
固定資産税や修繕費など継続的コスト
不動産を所有し続けることで発生する費用は、決して無視できるものではありません。
たとえ利用していない不動産であっても、固定資産税や都市計画税といった税負担は継続的に発生します。また、老朽化した建物については修繕や維持管理が必要であり、放置すると建物の資産価値は下がる一方です。
こうしたコストを見落としていると、相続人にとって“価値ある遺産”ではなく、“重荷”となる不動産になってしまう恐れがあります。特に空き家や郊外にある使い道のない土地などは、管理責任だけが相続人に押し付けられる状況になりがちです。
市場価格の変動リスク
不動産市場は常に一定ではなく、価格の変動リスクを伴います。
例えば、相続時点では5,000万円と評価されていた不動産でも、将来的な地価の下落や建物の老朽化によって、売却時には大幅に価値が下がることもあります。
一方で、相続税の計算は原則として相続開始時の評価額で行われるため、「税金は高く支払ったのに、実際の売却額は少なかった」という不均衡が起きることがあります。これは、現金や金融資産では起こりにくい、不動産特有のリスクだといえるでしょう。
複数人相続時の共有不動産トラブル
共有名義での不動産相続は、相続人間のトラブルの温床となります。
遺産分割協議で不動産を共有とした場合、売却・賃貸・修繕といったあらゆる意思決定には原則として全員の合意が必要です。一人でも反対すれば物件の処分ができないため、長期的な膠着状態に陥ることも珍しくありません。
また、共有者が亡くなると、次の相続でさらに共有者が増え、登記関係が複雑化する“数次相続”の問題も発生します。こうした状況を放置してしまうと、不動産の活用どころか、相続人同士の関係性が悪化する原因にもなります。
相続税対策としての不動産活用の限界
「不動産を持っていれば相続税が下がる」という考え方には、大きな誤解が含まれています。
確かに、小規模宅地等の特例や貸家建付地評価による圧縮効果は魅力的です。しかし、適用には厳密な条件があり、ケースによっては全く効果を発揮しないこともあります。
さらに、節税効果を狙って新たにアパートを建築した場合、「思ったより入居率が上がらない」「管理コストがかかる」「修繕費がかさむ」など、本来の目的を達成できないまま負担だけが残るケースも少なくありません。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、こうした“見せかけの節税”に惑わされることなく、本当に意味のある相続対策をお客様と一緒に考えます。不動産の有効性とリスクを天秤にかけたうえで、最も納得できる方法をご提案いたします。
不動産活用における相続人間のトラブル事例

売却・賃貸方針の不一致
不動産を共有で相続した場合、運用方針を巡って相続人間で意見が食い違うことは珍しくありません。
例えば、兄は「売却して現金化したい」と考え、妹は「思い出のある家なので残したい」と希望する。こうした考え方の違いが表面化すると、感情的な衝突を引き起こし、結果として遺産全体の分割協議が進まなくなる可能性があります。
特に、東京都世田谷区のように地価の高い地域では、資産価値が高いがゆえに感情と現実のバランスを取るのが難しい場面もあります。不動産には数字だけでは計れない「思い入れ」や「期待値」が存在するため、話し合いが長引く傾向があります。
維持費の分担問題
不動産を相続したあとには、定期的な維持・管理に関する費用が発生します。
ところが、その費用を誰が・どれだけ負担するのかが決まっていない場合、費用負担の不公平感から不満が生じやすくなります。 たとえば長男が建物の修繕費を支払っているのに、他の兄弟姉妹が一切関与せず、家賃収入だけを受け取っているような状況では、対立が深まるのも無理はありません。
相続対策の段階で「管理責任」や「コスト分担のルール」を定めておくことが、後のトラブル回避につながります。
地主型相続人と生活者型相続人の対立
地主型相続人(投資や管理の視点で不動産を見る人)と、生活者型相続人(その不動産で暮らしている人)との間には、意見の違いが大きくなりがちです。
たとえば、ある兄弟は都内に住んでおり、投資物件として活用したいと考える一方、もう一方の兄弟はその家に住み続けたいと思っている。この立場の違いが、感情のもつれに発展することが多く見られます。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、こうした立場の異なる相続人に対しても公平かつ中立的な調整を行い、家族関係を壊さないための支援を大切にしています。
法定相続分と現物分割の矛盾
不動産は分割が難しい資産であるため、法定相続分に応じた公平な分割が実現しにくいという特性があります。
「法定相続分では1/3ずつ分けるはずが、建物は分けられないから兄が住んで、妹には他の資産で…」というように、“代償分割”や“共有分割”が必要になることが多く、その調整が複雑化します。
さらに、代償金(お金で差額を補う)を準備できないケースでは話がまとまらず、遺産分割調停に発展するケースもあります。 不動産に強い執着がある相続人がいると、なおさら協議は困難になります。
トラブル回避のための事前設計の重要性
不動産を原因とする相続人間のトラブルを回避するには、生前の準備がすべてと言っても過言ではありません。
遺言書の作成、家族会議の実施、そして専門家によるアドバイスを受けながらのプランニングは、家族を守るための最も有効な手段です。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、遺言だけでなく、家族信託や生命保険、不動産の共有解消方法までをトータルに設計し、想定されるトラブルの芽を事前に摘み取ります。相続人が争うことなく、*「円満に受け継げる仕組み」の提供を重視しています。
不動産相続による税務上の注意点

評価額と実勢価格の乖離に伴うリスク
不動産の相続では「評価額」と「実際の市場価格」が一致しないことが大きな税務リスクを生み出します。
相続税の計算に使われるのは「路線価」や「固定資産税評価額」をベースとした価格ですが、実際に売却するときの金額(実勢価格)は、それより高くも低くもなる可能性があります。
例えば、東京都世田谷区のような地域では、路線価が比較的安定している一方、人気エリアにおける実勢価格の上昇により、評価との差が生じやすくなります。 逆に、郊外や築年数の古い建物では、評価は高くても売却時には値がつかないという状況もあります。
このように「高く評価されたのに、安くしか売れなかった」ということになれば、納税だけが重くのしかかり、相続人の金銭的負担は極めて大きくなります。
小規模宅地等の特例の落とし穴
不動産の相続対策において「小規模宅地等の特例」は非常に強力な節税手段ですが、条件を満たさなければ適用されません。
たとえば、被相続人と同居していた配偶者や子がその土地を引き継ぎ、引き続き住み続けるなどの前提条件があります。ところが、被相続人が一人暮らしで子どもは別居している場合などは、特例が適用されず減税効果を受けられないことがあります。
このような適用漏れにより、本来想定していた相続税対策が機能せず、結果として高額な相続税を支払うことになったというケースも珍しくありません。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、特例の適用可否について詳細な調査とシミュレーションを行い、安全なプラン設計を徹底しています。
不動産売却時の譲渡所得税
相続した不動産を売却する際、譲渡所得税(いわゆるキャピタルゲイン課税)が課される可能性があります。
特に、相続税を納めるために不動産を売却する場合、「二重課税になった」と感じる相続人も多いのが実情です。
譲渡所得税の計算では、相続時の取得費に加え、相続税の一部を取得費加算できる制度もありますが、適用期間が限られていたり、金額に制限があるなど注意が必要です。
また、不動産の売却益が大きい場合には、住民税も含めて20%を超える税負担が生じるため、「税金を払って終わりだった」と後悔する方も少なくありません。
アパート建築の節税神話の真相
近年では「アパート建築による相続税対策」が一部で流行しましたが、その多くがうまくいっていないのが実情です。
不動産を貸家として運用することで評価額が下がる仕組みを利用したものですが、入居率が低かったり、維持費が高額だったりすると、収益は思ったほど上がらず、むしろ負債だけが残るケースが出ています。
さらに、建築費をローンで賄った場合、借金が相続財産に含まれることで相続後の生活設計を圧迫することもあり、本末転倒の結果に終わることが多いのが現状です。
このような「節税だけを目的としたアパート建築」は、中長期的な視点に欠けた危険な相続対策だといえるでしょう。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所が提案する税務戦略
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、「税金を減らすこと」だけを目的とした短絡的な対策は行いません。
むしろ、お客様の「家族構成」「資産の全体像」「将来の希望」「相続人の状況」などを丁寧にヒアリングした上で、納税・分割・活用すべてを考慮した総合戦略をご提案しています。
税務上のミスや抜け漏れがないよう、各種の特例や控除を最大限活用しつつ、不動産だけに頼らないバランス型の相続対策を実現します。必要に応じて弁護士や不動産鑑定士、信託専門家とも連携し、東京都世田谷区から全国の皆様に最善のご支援を提供しています。
不動産以外の相続対策とその組み合わせ方

生命保険を活用した納税資金対策
相続対策において、不動産だけに頼らず「生命保険」をうまく活用することは非常に有効な手段です。
生命保険は、現金として速やかに受け取れるため、納税資金としてそのまま充当できる点が大きなメリットです。また、法定相続人1人につき500万円までの非課税枠が適用されるため、相続税の軽減にもつながります。
不動産は相続後すぐには現金化しにくいため、納税資金の準備としては不向きな面もあります。 そのギャップを補完する意味でも、生命保険は非常に有効です。齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、お客様の年齢や家族構成に応じた生命保険活用のアドバイスを行っております。
家族信託による柔軟な資産管理
不動産や現金、有価証券などを家族信託に組み込むことで、より柔軟な資産管理と相続対策が可能になります。
例えば、親が認知症になってしまった場合でも、信託契約を結んでおくことで、後見制度を利用せずとも財産管理や処分ができるというメリットがあります。
不動産を所有する場合、将来的に処分や修繕の意思決定が必要になる場面が必ず訪れます。その際に本人の判断能力が失われていると、対応が難しくなることがありますが、家族信託を活用すれば、あらかじめ信頼できる家族に管理・運用を託すことが可能です。
遺言書作成で意志を明確にする
「誰に何をどう残すか」を明確にすることは、相続トラブルを防ぐうえで最も基本的で効果的な対策です。
法的に有効な遺言書を作成することで、法定相続分とは異なる配分も可能となり、ご自身の思いをしっかりと形にして残すことができます。
特に、不動産は物理的に分けにくいため、遺言によって誰が所有するかを明示することで、後々のトラブルを未然に防げます。 齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、司法書士・弁護士と連携し、遺言書作成サポートも対応しております。
有価証券や現金資産のバランス運用
相続財産の中に一定の現金や有価証券を組み込んでおくことは、相続後の分割や納税対応をスムーズにするために不可欠です。
不動産ばかりを所有していると、分けにくく、流動性に欠けるため、「不動産を売らないと分けられない」という状況に陥ってしまいます。
有価証券や現金資産をバランスよく保持しておくことで、相続人ごとの配分の柔軟性が高まり、“争族”を避ける対策として非常に効果的です。また、納税資金としても活用しやすいため、資産全体の中での調整が可能です。
ワンストップ支援で叶える多角的相続対策
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、不動産に偏らず、生命保険・信託・現金・有価証券・遺言といった複数の手段を組み合わせた“多角的な相続対策”をご提案しています。
相続というのは、税金だけでなく、感情や生活、将来の変化までも考慮する必要がある極めて複雑な課題です。
そのため、当事務所では税理士のみならず、弁護士・司法書士・保険代理店・不動産会社などと密に連携し、お客様一人ひとりの事情に合わせた完全オーダーメイドの対策を実施しております。
東京都世田谷区を拠点とする当事務所は、「相続対策の入り口から出口まで、全てを一元化してご支援」することで、安心と納得をお届けするパートナーであり続けたいと考えています。
Q&A:よくあるご質問にお答えします

Q1. 不動産は必ず相続対策に向いているのですか?
必ずしも不動産が相続対策に適しているとは限りません。
不動産は資産価値が分かりやすく、評価の圧縮効果があることから相続税対策として使われることが多いですが、現金化しにくい・管理負担がある・相続人間での分割が難しいなどのデメリットも抱えています。不動産の相続は、家族構成や資産全体のバランスに応じた慎重な判断が必要です。
Q2. 相続税を減らすために不動産を購入すべきですか?
不動産購入は節税効果だけで判断すべきではありません。
将来的な収益性や流動性、維持費用、相続人の負担も考慮すべきです。短期的な節税目的でアパート経営などを始めた結果、思ったような入居率にならず赤字が続くケースも多く見られます。 当事務所では、購入前にキャッシュフローや税負担の試算を行い、必要に応じて見直しをご提案いたします。
Q3. 遺言書があっても不動産トラブルは起こりますか?
遺言書があっても、内容が曖昧であればトラブルが起きる可能性はあります。
特に不動産に関しては「誰に所有させるのか」「他の相続人との調整はどうするのか」などが明記されていないと、相続人間での感情的な対立に発展することもあります。 当事務所では、専門家が遺言内容の精査やアドバイスを行い、実効性の高い遺言書作成を支援いたします。
Q4. 生前贈与と相続、どちらが得ですか?
ケースバイケースですが、目的と状況によって使い分けるのが効果的です。
たとえば、不動産を生前に贈与すれば将来の争いを防げますが、その分、贈与税が高額になる可能性もあります。一方、相続で渡す場合は税率の調整が可能ですが、納税や分割の問題が後に残ることもあります。 齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では、贈与と相続を組み合わせた最適なスキーム構築をご提案しております。
Q5. 齋藤久誠公認会計士・税理士事務所では不動産評価も対応していますか?
はい、専門家と連携して不動産の評価・調査にも対応しています。
相続税申告や財産分割のために不動産の評価を行うことは極めて重要です。当事務所では、不動産鑑定士や不動産会社と協力しながら、税務上適切でかつ現実的な評価を行い、納税額のシミュレーションも含めて総合的に支援しています。
Q6. 不動産売却による納税資金確保のタイミングは?
原則、相続開始から10か月以内に納税が必要になるため、売却は早期に判断すべきです。
売却に時間がかかることもあるため、事前に準備を進めておくことが大切です。市場の動向や売却時期を見誤ると、希望額で売れず納税に支障が出るリスクがあります。 必要に応じて、当事務所が売却計画のアドバイスをいたします。
Q7. 家族信託と不動産活用は同時にできますか?
はい、家族信託と不動産活用は非常に相性が良く、併用が可能です。
特に、将来の判断能力低下を見越して不動産を信託化しておけば、認知症などで本人の意思確認ができなくなった後も、信託受託者が売却や管理を継続できます。 当事務所では、家族信託契約の設計から実行までトータルサポートいたします。
まとめ

不動産は相続対策の中でも重要な資産であり、多くの方が「残す財産」として活用を検討されます。
確かに、不動産には評価額を圧縮できるなどの利点がある一方で、流動性の低さや管理コスト、相続人間のトラブル、税務上の落とし穴など多くのデメリットが潜んでいるのも事実です。特に東京都世田谷区のような都市部では、地価や評価の高さが裏目に出てしまうことも少なくありません。
また、「相続税を減らすために不動産を購入する」といった短絡的な考え方では、長期的に不良資産を抱えてしまうリスクもあります。不動産の相続には、節税だけでなく、納税資金の確保・分割のしやすさ・相続人の生活設計など、あらゆる側面からの配慮が必要です。
そこで大切なのが、不動産だけに頼らず、多角的に相続対策を設計すること。
生命保険、家族信託、現金・有価証券、遺言書などの手段を組み合わせることで、相続に関する課題をバランスよく解決することができます。
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所(東京都世田谷区)では、税務・法律・不動産・保険の各分野の専門家と連携し、お客様の思いやご家族の将来像を大切にしながら、オーダーメイドの相続対策を提供しています。
「不動産を持っているから安心」「相続税対策はとりあえず済んでいる」という感覚のまま放置せず、一度、専門家とともに資産の全体像を見直してみませんか?
将来の不安を取り除き、納得できる形で資産を次世代に引き継ぐために、齋藤久誠公認会計士・税理士事務所が全力でサポートいたします。

(東京税理士会玉川支部所属(登録番号:139151号)
FAQ
よくあるご質問
- 電話・メールでの税務相談は可能ですか?
- 当事務所の方針としまして、ご相談の際には、直接お会いしてお話させていただいております。ただし、場合によっては、お電話にて相談を承る場合もあります。詳しくは、一度お電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 相談に行く際、事前に準備しておくべきことはありますか
- 初回面談はお客様のご相談事項をお伺いすることが中心です。ご相談事項に関連する資料をご準備ください。
- 費用はいくらかかりますか?
- お支払いいただく費用はご依頼事項により異なります。ご依頼いただく前にお見積書を作成させていただきますのでご依頼ください。
- 駐車場はありますか?
- 当事務所は専用駐車場を用意しておりません。近隣の駐車場をご利用いただくか公共交通機関でのご来訪をお願いいたします。
- 予約なしで相談できますか?
- 当事務所は完全予約制とさせていただいております。ご相談をご希望の際は、事前に電話またはメールでのお問合せをお願い致します。
information
事務所情報

- 住所
-
〒158-0094
東京都世田谷区玉川3-11-1柳小路東角3階310
- tel
- 050-3639-1594
- 営業時間
-
平日 9:00〜18:00 / 土曜 9:00〜12:00
当社は完全予約制となっております。
- メールアドレス
- saito@cpatax-office.com
- 定休日
- 日、 祝日
- 最寄り駅
- 東急田園都市線・大井町線『二子玉川』駅 徒歩3分