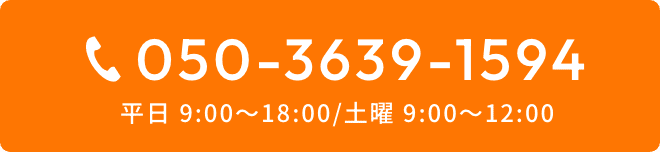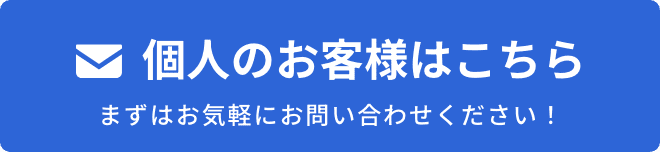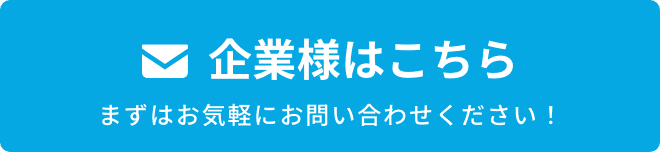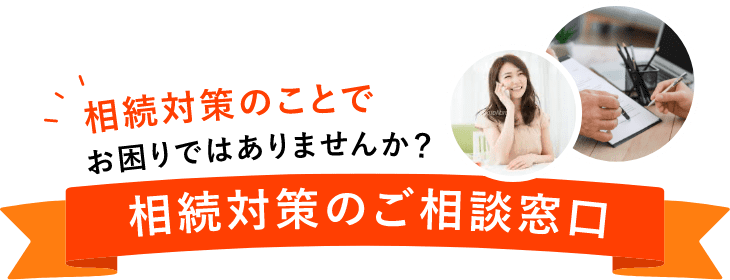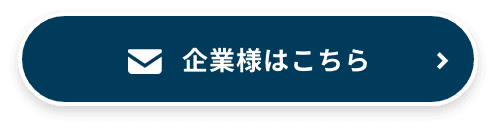ブログ
相続割合の決め方について—齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所が解説

相続の際に避けて通れない課題の一つが「遺産の分割割合」の決定です。遺産分割は、財産をどのように分けるかだけでなく、家族や親族間の信頼関係にも大きな影響を与えます。特に、日本では相続をめぐる争いが後を絶たないと言われており、感情的な対立が原因で親族間の関係が悪化するケースも少なくありません。そのため、相続における適切な割合の決め方を理解し、事前に準備を進めることが重要です。
相続の割合を決める際には、法律に基づくルールがある一方で、家族間での話し合いによる調整も求められます。法律を守るだけでなく、相続人全員が納得し、将来的なトラブルを防ぐためには、適切な知識と冷静な対応が不可欠です。また、遺産の内容や家族構成によって最適な手続きは異なるため、専門家の助言を受けながら進めることが望ましいと言えます。
東京都世田谷区にある「齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所」では、相続に関する深い知識と豊富な経験を持ち、個々の状況に合わせた最適なアドバイスを提供しています。遺産分割に関するお悩みを抱えている方は多いものの、どこから手をつければよいのかわからずに手遅れになることもあります。当事務所では、遺産分割の基本的な知識から具体的な手続きの進め方まで、一貫してサポートを行います。
この記事では、相続割合を決める際に知っておくべき基本的な考え方や法的なルール、さらにスムーズな話し合いを実現するためのコツを詳しく解説していきます。この記事を通じて、相続に関する不安や疑問が少しでも解消されることを願っています。そして、もし専門的なサポートが必要であれば、「齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所」にご相談ください。あなたの家族の未来を守るお手伝いを全力でさせていただきます。
法律に基づく相続割合の基本

法定相続分の概要
日本の法律では、相続割合は民法に定められた「法定相続分」が基本となります。この法定相続分は、被相続人が遺言書を残していない場合に適用される基準であり、家族構成によってその割合が決まります。法定相続分のルールは、遺産分割を公平かつ明確に行うために重要な役割を果たしています。
例えば、配偶者と子供が相続人となる場合、配偶者が遺産の1/2、残りの1/2が子供たちに均等に分配されます。一方、配偶者と直系尊属(被相続人の両親や祖父母)が相続人の場合、配偶者が2/3、直系尊属が1/3を分け合います。また、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を分配します。
ただし、これらの割合はあくまで法律上の基準であり、必ずしも相続人全員の合意に基づく最終的な分割方法と一致するわけではありません。家族間での話し合いや遺言書の内容に応じて、具体的な割合が変わることが一般的です。
遺言書がある場合の影響
遺言書は、法定相続分に優先する重要な文書です。被相続人が遺言書で具体的な割合や分割方法を指示している場合、原則としてその内容が尊重されます。これにより、被相続人の意思を直接的に反映させた遺産分割が可能になります。
ただし、遺言書が有効であるためには、法的に定められた形式や条件を満たしている必要があります。例えば、自筆証書遺言の場合、全文が被相続人自身の手書きで作成されていなければ無効となる場合があります。また、公正証書遺言の場合は、公証人の立会いのもとで作成されるため、形式上の問題や無効となるリスクが低いというメリットがあります。
さらに、遺言書に基づく分割が行われる際にも、遺留分と呼ばれる相続人の最低限の取り分を侵害しないことが求められます。このため、遺言書の内容に基づきつつ、相続人全員が納得する形での話し合いが重要となります。
特別受益と寄与分
相続においては、特別受益や寄与分の存在が相続割合を左右することがあります。特別受益とは、被相続人が生前に相続人の一部に対して財産を贈与した場合、それを遺産分割時に考慮する仕組みです。例えば、結婚資金や住宅購入の援助が特別受益に該当します。この特別受益がある場合、その分を遺産に加算して計算し、相続割合を調整します。
一方、寄与分は、相続人の中で特に被相続人の財産の維持や増加に寄与した者がいる場合、その貢献を評価して分割割合を優遇する制度です。例えば、被相続人の介護を長期間行ったり、家業の発展に大きく貢献した場合が該当します。これらの要素を考慮した分割案を作成することで、公平かつ納得のいく相続が実現します。
遺産分割協議書の必要性
相続が開始された後、相続人全員で行う遺産分割の話し合いを遺産分割協議と言います。この結果を記録する文書が遺産分割協議書であり、法的効力を持つ重要な書類です。遺産分割協議書には、財産の分割内容や相続人全員の同意を明確に記載し、全員が署名・押印する必要があります。
遺産分割協議書が作成されていない場合、土地や建物などの不動産の登記変更や、預貯金の引き出しなどができず、手続きが滞る可能性があります。また、後々のトラブルを防ぐためにも、協議内容を明確に記録することが重要です。齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、正確で法的に有効な遺産分割協議書の作成をサポートしています。
家族信託の活用
家族信託は、近年注目されている財産管理の手法であり、高齢化社会の中でその重要性が増しています。この制度は、財産を信頼できる家族に託し、その管理や運用を行わせる仕組みです。特に、認知症リスクの高まりによる財産管理の困難化を防ぐための有効な方法として活用されています。
家族信託では、被相続人が生前に自分の意思で財産の管理者(受託者)を指定し、運用方法や分配方法を指示できます。この仕組みにより、相続開始後もスムーズな財産分割が可能となり、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。また、遺言書では対応できない生前の財産管理にも対応できる点が大きなメリットです。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、家族信託の導入支援や、信託内容の設計、法的手続きのサポートを提供しています。複雑な仕組みであるため、専門家の助言を受けながら進めることをおすすめします。家族信託を上手に活用することで、大切な財産を守りながら、安心して次世代に引き継ぐことが可能です。
相続割合を話し合いで決めるポイント
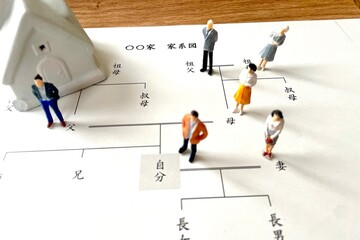
家族間の合意の重要性
法律に基づく相続割合は、相続人間での基本的な指針を提供するものですが、それが全てではありません。遺産分割においては、家族間での話し合いによる合意が最も重要な要素となります。法定相続分は公平性を意識した基準ですが、家族の事情や希望を考慮すると、それだけでは満足のいく解決に至らない場合があります。
例えば、特定の相続人が被相続人の介護を長年続けてきた場合や、事業を引き継ぐことが決まっている場合など、実際の状況に基づいて柔軟な分割が必要になることもあります。このような状況では、相続人全員が納得する形で合意に達することが、相続を円満に進めるための鍵となります。
さらに、話し合いが行われず、強引に分割が進められると、家族間の信頼関係が損なわれるだけでなく、後々のトラブルや裁判沙汰に発展するリスクも高まります。これを避けるためには、冷静かつ誠実に話し合いを行い、全員が納得する形で遺産分割を進める努力が必要です。
東京都世田谷区の「齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所」では、話し合いの場をスムーズに進めるためのサポートを提供しています。専門家が関与することで、感情的な対立を抑え、冷静かつ建設的な話し合いを実現することが可能です。
話し合いの進め方
相続の話し合いを進める際には、次のようなポイントを押さえることが成功の鍵となります。
- 全員が平等に発言できる場を設けること
話し合いでは、全ての相続人が対等な立場で意見を述べることができる環境を整えることが重要です。一部の相続人が発言を独占したり、他者の意見を否定することがないよう配慮します。 - 感情的にならないよう心掛けること
相続は感情的になりやすいテーマです。しかし、感情的な言動はトラブルの原因となるため、冷静に話し合いを進める努力が必要です。 - 財産の全体像を明確にすること
遺産分割をスムーズに進めるためには、遺産の全体像を正確に把握することが欠かせません。不動産や預貯金、株式など、全ての財産をリストアップして価値を明確にします。
また、話し合いの場では、事前に「こうするべき」という結論を押し付けないことが重要です。あくまで話し合いを進めながら、全員が納得できる結論に至ることを目指します。
専門家のサポート
相続の話し合いにおいて、専門家のサポートを受けることは大きなメリットとなります。専門家は、法律や税務の知識を駆使しながら、話し合いを客観的にサポートします。また、家族間での感情的な対立が生じた際にも、中立的な立場から冷静なアドバイスを行うことができます。
専門家を交えることで、以下のような効果が期待できます。
- 法律や税金に関する正しい情報を提供し、誤解や不安を解消する。
- 客観的な視点から、公平で合理的な分割案を提案する。
- 話し合いが行き詰まった場合に、代替案や妥協点を提示する。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、専門的な知識を活用し、相続人全員が納得する形での遺産分割をサポートしています。
公平な分割案の作成
公平な遺産分割を実現するためには、財産の価値や相続人の状況を適切に評価することが重要です。例えば、不動産や株式のように現金化しにくい資産が含まれる場合、それらの資産を誰がどのように取得するかを慎重に決定する必要があります。
また、相続人それぞれの事情を考慮することも大切です。たとえば、ある相続人が被相続人の介護を担当していた場合、その貢献を評価し、他の相続人と調整を行うことが求められる場合があります。公平性を保ちながらも、実際の状況に合った分割案を作成することで、全員が納得感を持って合意に至ることができます。
公平性を確保するために、財産の評価額を専門家に依頼し、分割案を明確にすることも一つの方法です。齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、複雑な財産評価や分割案の作成を丁寧にサポートします。
東京都世田谷区での事例紹介
東京都世田谷区にお住まいのAさんの事例をご紹介します。Aさんのご家族では、遺産に不動産と預貯金が含まれており、相続人はAさんの配偶者と2人の子供でした。しかし、不動産の評価額が高く、現金が不足していたため、全員が納得する分割案を作成するのが難しい状況でした。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所がサポートした結果、以下の手順で問題を解決しました。
- 不動産の適正な評価額を算出し、相続人間での共有を防ぐために売却を提案。
- 売却益を預貯金と合わせて現金化し、相続人全員に公平に分配。
- 子供たちの意見を取り入れ、必要に応じて代償金を支払う形で調整。
このように、専門家のアドバイスを活用することで、トラブルを未然に防ぎ、全員が納得する形で遺産分割を終えることができました。この事例は、専門的な知識を活用したサポートが、スムーズな相続手続きにおいていかに重要であるかを示しています。
相続の専門家を活用するメリット

手続きの簡略化
相続手続きは、多くの場面で複雑さを伴います。不動産の名義変更、預貯金の解約、税務申告など、相続に関連する手続きは一つ一つが専門知識を必要とするため、全てを自身で進めるのは現実的に困難です。専門家を活用することで、こうした煩雑な手続きをスムーズかつ効率的に進めることが可能になります。
専門家は、まず財産目録を作成し、相続財産の全体像を明確にします。これにより、相続人全員が財産の内容を正確に把握でき、無駄な争いを防ぐことができます。また、税務申告においても、相続税の申告期限を守るためのスケジュール管理や必要書類の準備などを的確に進めてくれます。
さらに、専門家は相続手続き全般をワンストップで対応することが可能です。不動産評価の手配から遺産分割協議書の作成、そして相続税申告まで、一貫したサポートを提供するため、相続人がそれぞれ異なる業者や機関とやり取りする手間が省けます。こうしたプロセスの簡略化は、相続人にとって大きな精神的負担の軽減となるだけでなく、時間や労力の節約にもつながります。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、相続に関する全ての手続きを一括してサポートし、ご家族が安心して次のステップへ進めるようお手伝いします。
トラブルの予防
相続におけるトラブルの多くは、家族間の感情的な対立や情報不足によって引き起こされます。専門家が関与することで、第三者の冷静な視点からアドバイスを受けられるため、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。
例えば、相続人同士の意見が対立した場合でも、専門家が公平な立場で意見をまとめ、全員が納得できるような解決案を提案します。また、財産の価値や分割方法についての誤解を解消し、事実に基づいた話し合いができるようサポートします。こうした取り組みにより、相続人間の不和を防ぎ、家族関係の維持に貢献します。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、トラブルのリスクを最小限に抑えながら、公平で納得感のある相続を実現するための支援を行っています。
法的リスクの軽減
相続手続きでは、法律を正確に理解し、適切な対応を行うことが求められます。法律の解釈を誤ったり、必要な手続きを怠ると、後々法的なトラブルに発展する可能性があります。専門家を活用することで、こうしたリスクを軽減することが可能です。
例えば、遺産分割協議書の作成において、法的に有効な内容となるよう専門家がチェックを行うことで、後から無効とされるリスクを防ぐことができます。また、相続税申告では、税法に基づいた正確な計算を行い、過不足のない納税が可能です。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、法的なリスクを最小限に抑えるため、最新の法律や判例に基づいたアドバイスを提供しています。
相続税対策の提案
相続税は、財産の種類や額に応じて大きな負担となる場合があります。特に、不動産が多く現金が少ないケースでは、相続税の支払いが困難になることがあります。専門家は、こうした状況に対処するための具体的なプランを提案します。
例えば、生前贈与を活用した相続税の軽減や、不動産の評価額を適切に見直すことで税負担を減らす方法があります。また、小規模宅地等の特例など、税制優遇措置を最大限活用するための手続きをサポートします。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、個々の状況に応じた相続税対策を提案し、負担を軽減するための最適な方法を提供しています。
安心感の提供
相続手続きは、法律や税務の知識が必要なだけでなく、感情的な負担も大きいものです。特に、家族の一員を失ったばかりの時期に、複雑な手続きを進めなければならないことは、大きなストレスとなります。専門家のサポートを受けることで、こうした不安や負担を軽減し、安心して手続きを進めることができます。
また、専門家が関与することで、相続人全員が公平に扱われているという安心感を持つことができます。特に、財産の分割や税務において専門的な知識を持たない場合でも、専門家がしっかりとサポートしてくれることで、手続き全体を信頼して任せることができます。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、相続手続きの全てを安心して進められるよう、丁寧な説明とサポートを心掛けています。ご家族の未来を守るため、そして円満な相続を実現するために、ぜひご相談ください。専門家の力を借りることで、相続手続きがスムーズかつ安心して進められることを実感していただけるはずです。
遺産分割における心理的要因

感情的な対立の影響
相続の場面では、感情的な対立が大きな障害となることがあります。特に、被相続人の死による感情的な負担や、長年にわたる家族間の複雑な関係が背景にある場合、話し合いがスムーズに進まないことが多いです。遺産分割は、単なる財産の分け合いではなく、家族間の絆が試される場面でもあります。
感情的な対立は、過去のわだかまりや不満が再燃するきっかけになることがあります。例えば、幼少期からの親子間の格差や、兄弟姉妹間の競争意識などが原因で、遺産分割において公平性が疑われるケースが発生します。このような状況では、相続人間での信頼関係が損なわれ、最終的には裁判にまで発展する可能性もあります。
また、感情的な対立は、合理的な判断や妥協を難しくします。相続人が冷静さを失い、自分の権利を過剰に主張することで、他の相続人との関係がさらに悪化します。このような状況を避けるためには、全員が冷静に話し合いを行い、感情に流されないよう努めることが必要です。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、こうした感情的な問題を解消するためのサポートも行っています。専門家が第三者として関与することで、感情的な対立を抑え、冷静で建設的な話し合いを実現します。
公平性の重要性
相続における公平性は、全ての相続人が納得できる解決を目指す上で極めて重要です。公平性が感じられない分割案は、不満やトラブルを引き起こす原因となります。公平性を保つためには、財産の価値や相続人の貢献度を正確に評価し、全員にとって納得のいく分割案を作成することが必要です。
特に、不動産や株式などの評価が難しい財産が含まれる場合、専門家による正確な評価が求められます。さらに、家庭内で特定の相続人が被相続人の介護や支援に大きく貢献していた場合、その点を考慮した分配が公平性を確保する鍵となります。
公平性を実現するためには、家族全員が対話を重ね、相互理解を深めることが重要です。齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、こうした対話の場をサポートし、公平性を保ちながらスムーズな遺産分割をお手伝いします。
コミュニケーションの改善
相続人同士の適切なコミュニケーションは、遺産分割を円滑に進める上で欠かせません。多くの相続トラブルは、誤解や不信感が原因となって発生します。例えば、財産の内容や分割案に関する情報が十分に共有されていない場合、相続人間での不信感が高まることがあります。
コミュニケーションを改善するためには、相続人全員が対等に意見を述べる場を設けることが重要です。また、情報共有を徹底し、財産目録や分割案を透明性のある形で提示することで、誤解を防ぐことができます。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、コミュニケーションの円滑化を図るためのサポートを提供しています。専門家が話し合いの進行を支援することで、相続人全員が納得できる結論に至る手助けをします。
家族会議の活用
家族会議は、全員が意見を出し合い、相互理解を深めるための有効な手段です。定期的に家族会議を開くことで、遺産分割の進行状況を確認し、全員が納得感を持ちながら話し合いを進めることができます。
家族会議では、感情的になりすぎないよう、事前に議題を明確にしておくことが重要です。また、進行役を設けることで、話し合いが円滑に進むだけでなく、全員が発言しやすい環境を作ることができます。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、家族会議の進行役としてのサポートも行っています。中立的な立場からアドバイスを提供することで、話し合いがスムーズに進むようお手伝いします。
専門家による仲介
専門家が仲介役を務めることで、家族間の対立を最小限に抑え、冷静で合理的な遺産分割を実現することができます。専門家は、法律や税務の知識を活用しながら、相続人全員が納得する形での分割案を提案します。
また、専門家が関与することで、感情的な対立を抑え、客観的な視点から話し合いを進めることが可能になります。特に、相続税や特別受益、寄与分などの複雑な要素が絡む場合、専門家の助言は非常に有益です。
さらに、専門家が作成する分割案は、法的なリスクを最小限に抑えるよう設計されています。これにより、後から法的な問題が発生するリスクを防ぎつつ、全員が安心して相続手続きを進めることができます。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、家族間の話し合いが円満に進むよう全力でサポートしています。専門家による仲介を活用することで、スムーズで公平な遺産分割を実現し、家族全員が満足できる結果を目指します。相続に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
Q&A よくあるご質問にお答えします

Q1: 遺産分割で合意できない場合はどうなりますか?
遺産分割で合意が得られない場合、家庭裁判所で調停や審判を行う必要があります。調停は、裁判所の調停委員が仲裁役となり、相続人間の話し合いを促進する手続きです。調停が成立すれば、その内容に基づき遺産分割が行われます。しかし、調停で合意に至らない場合は審判に移行します。
審判では、裁判官が法律に基づき相続財産の分割を決定します。このため、相続人間の意向が十分に反映されない場合があるため、審判を避けるためにも調停で解決する努力が重要です。また、裁判所での手続きは時間がかかり、費用も発生します。専門家を早期に活用することで、家庭裁判所での手続きを回避し、相続人間での合意を目指すことが可能です。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、家庭裁判所に頼る前に相続人間の合意形成をサポートし、スムーズな遺産分割を実現するお手伝いをします。
Q2: 特別受益はどのように計算されますか?
特別受益とは、被相続人が生前に特定の相続人へ与えた財産や利益を、遺産分割時に考慮する仕組みです。特別受益がある場合、その金額を遺産総額に加算して分割割合を計算します。たとえば、生前贈与として住宅購入資金や結婚資金を受け取った場合が該当します。
特別受益の計算では、まず遺産総額に特別受益の金額を加算し、その合計を基に相続割合を計算します。その後、特別受益分を差し引いた金額がその相続人の最終的な取り分となります。ただし、特別受益の範囲や金額については、相続人間で争いになることも多いため、専門家の助言を受けながら進めることが重要です。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、特別受益の計算や合意形成をサポートし、全員が納得する形での遺産分割を支援します。
Q3: 家族信託と遺言書の違いは?
家族信託と遺言書は、どちらも相続に関する手段ですが、目的や適用範囲が異なります。遺言書は、被相続人が死亡した後の財産分配を指定するものであり、財産の管理は死後に開始されます。一方、家族信託は生前に財産管理を開始する仕組みで、被相続人の意思や状況に応じて柔軟に運用できます。
例えば、認知症のリスクがある場合、家族信託を利用することで、信頼できる家族に財産の管理を任せつつ、自分の意思を反映させた運用が可能です。一方、遺言書は法的効力が明確であり、手続きがシンプルなため、多くのケースで利用されています。どちらを選ぶべきかは、被相続人の状況や希望に応じて検討が必要です。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、家族信託と遺言書の違いを詳しく説明し、それぞれの利点を活かした提案を行っています。
Q4: 遺言書がない場合のリスクは?
遺言書がない場合、相続は法定相続分に基づいて行われることが基本となります。しかし、これにはいくつかのリスクがあります。まず、相続人間で意見が対立し、遺産分割の話し合いがスムーズに進まない可能性があります。また、遺産の内容や状況によっては、法定相続分に従った分割が公平ではないと感じられる場合もあります。
さらに、遺産分割協議が長引くと、不動産や株式の管理が不十分となり、資産価値が下がるリスクも生じます。特に、不動産が共有名義となる場合、売却や運用が難しくなり、トラブルが発生する可能性があります。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、遺言書がない場合でも、専門的なサポートを通じて相続人間の合意形成を促し、リスクを最小限に抑える方法を提案します。
Q5: 相続税対策には何が必要ですか?
相続税対策として重要なのは、生前からの計画的な取り組みです。例えば、生前贈与を活用することで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。年間110万円までの贈与であれば非課税となるため、これを毎年利用することで大きな節税効果が得られます。
また、小規模宅地等の特例を活用することで、不動産の評価額を大幅に引き下げることが可能です。この特例を適用するには、一定の要件を満たす必要があるため、事前に専門家の助言を受けることが重要です。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、個々の状況に合わせた相続税対策を提案し、税負担を軽減するための最適な方法を提供しています。
Q6: 遺産分割協議書はどのように作成しますか?
遺産分割協議書は、遺産の分割内容を明確に記載した書面であり、相続人全員の同意を示す重要な証拠となります。この書類がないと、不動産の名義変更や預貯金の解約が進まない場合があるため、法的に有効な形で作成する必要があります。
遺産分割協議書を作成する際には、財産の全容を正確に把握し、それぞれの相続人が取得する財産を具体的に記載します。また、全員の署名と押印が必要となるため、内容に全員が納得していることが重要です。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、正確で法的に有効な遺産分割協議書の作成をサポートし、手続きがスムーズに進むようお手伝いします。
Q7: 家族間で合意が取れない場合、どのように対処しますか?
家族間で合意が取れない場合、中立的な第三者を交えた話し合いや調停が有効です。専門家が仲介役を務めることで、感情的な対立を防ぎ、冷静かつ客観的な議論が可能になります。
また、専門家は公平な視点からアドバイスを提供し、全員が納得できるような解決策を提案します。調停や裁判を避けるためにも、専門家の力を借りて早期に問題を解決することが重要です。
齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所では、家族間の合意形成をサポートし、円満な遺産分割を実現するためのお手伝いをしています。
まとめ

相続割合の決め方は、法律に基づく基準を理解することが出発点ですが、それだけでは十分ではありません。法律が示す基準はあくまで目安であり、実際には家族間の合意形成が極めて重要な役割を果たします。公平で納得のいく遺産分割を実現するためには、相続人全員が互いに対話を重ね、それぞれの立場や事情を尊重し合う姿勢が求められます。
相続手続きは複雑で、多くの知識や労力が必要です。財産目録の作成や遺産分割協議書の作成、さらには相続税申告に至るまで、どれもが専門的な知識を必要とするものです。こうした手続きが滞ると、相続が長期化し、結果として家族間の不和やトラブルを引き起こす可能性があります。そのため、信頼できる専門家のサポートを受けることが、スムーズで安心な相続手続きの実現に欠かせません。
「齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所」では、東京都世田谷区を拠点に、相続に関するあらゆるご相談に対応しています。法律や税務の専門知識を駆使しながら、相続人全員が納得できる解決を目指して、親身にサポートを提供しています。また、家族間での話し合いの進行や、専門的なアドバイスによる公平な分割案の作成を通じて、後のトラブルを未然に防ぐお手伝いをしています。
この記事を通じて、相続に関する基本的な知識を深めていただけたのなら幸いです。そして、相続の準備や手続きに不安を感じている方は、ぜひ「齋藤久誠 公認会計士・税理士事務所」にご相談ください。私たちは、お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案し、大切なご家族の未来を守るためのサポートを全力で行います。信頼できる専門家に相談することで、相続手続きがよりスムーズかつ安心して進められることを実感していただけるはずです。

(東京税理士会玉川支部所属(登録番号:139151号)
FAQ
よくあるご質問
- 電話・メールでの税務相談は可能ですか?
- 当事務所の方針としまして、ご相談の際には、直接お会いしてお話させていただいております。ただし、場合によっては、お電話にて相談を承る場合もあります。詳しくは、一度お電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 相談に行く際、事前に準備しておくべきことはありますか
- 初回面談はお客様のご相談事項をお伺いすることが中心です。ご相談事項に関連する資料をご準備ください。
- 費用はいくらかかりますか?
- お支払いいただく費用はご依頼事項により異なります。ご依頼いただく前にお見積書を作成させていただきますのでご依頼ください。
- 駐車場はありますか?
- 当事務所は専用駐車場を用意しておりません。近隣の駐車場をご利用いただくか公共交通機関でのご来訪をお願いいたします。
- 予約なしで相談できますか?
- 当事務所は完全予約制とさせていただいております。ご相談をご希望の際は、事前に電話またはメールでのお問合せをお願い致します。
information
事務所情報

- 住所
-
〒158-0094
東京都世田谷区玉川3-11-1柳小路東角3階310
- tel
- 050-3639-1594
- 営業時間
-
平日 9:00〜18:00 / 土曜 9:00〜12:00
当社は完全予約制となっております。
- メールアドレス
- saito@cpatax-office.com
- 定休日
- 日、 祝日
- 最寄り駅
- 東急田園都市線・大井町線『二子玉川』駅 徒歩3分